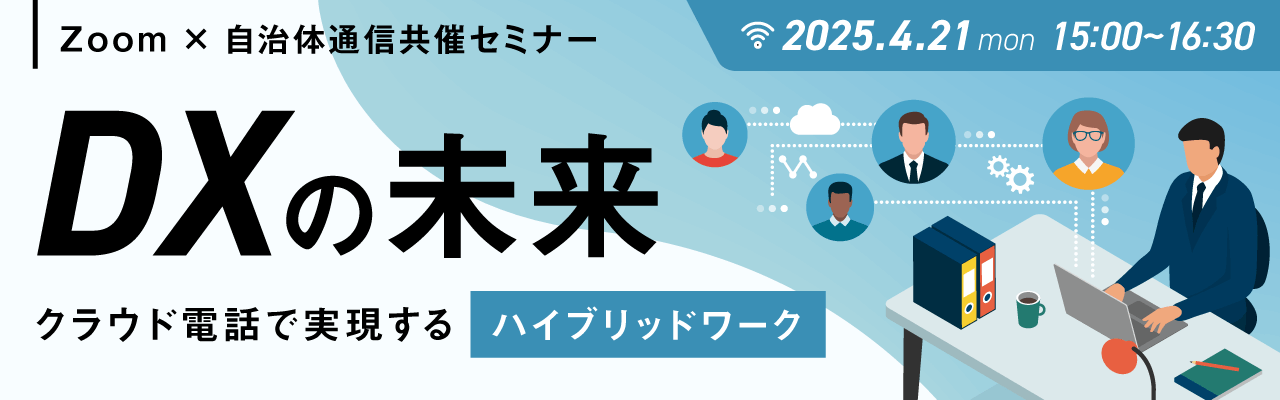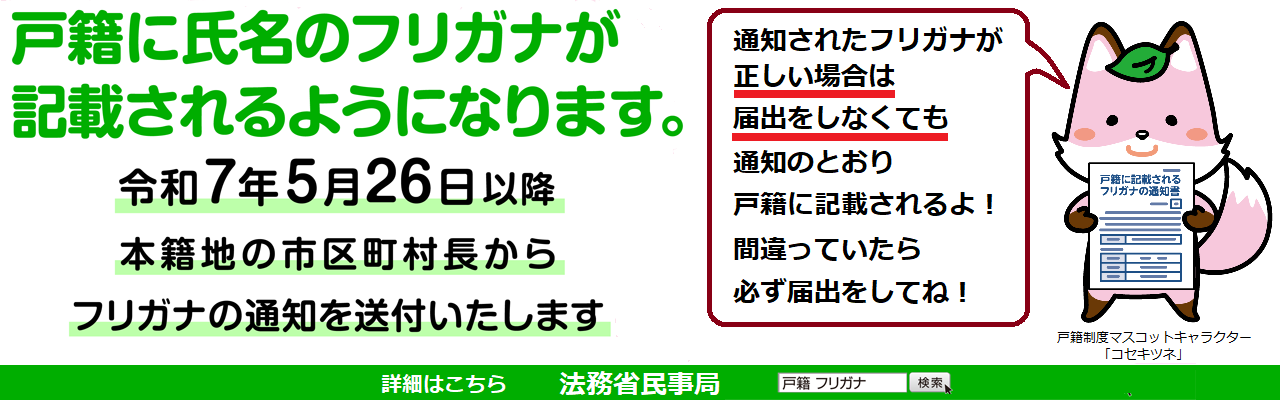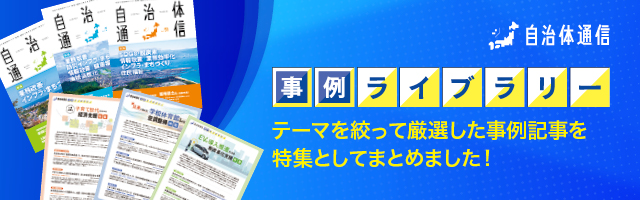DX~トランスフォーメーションの本質とは?
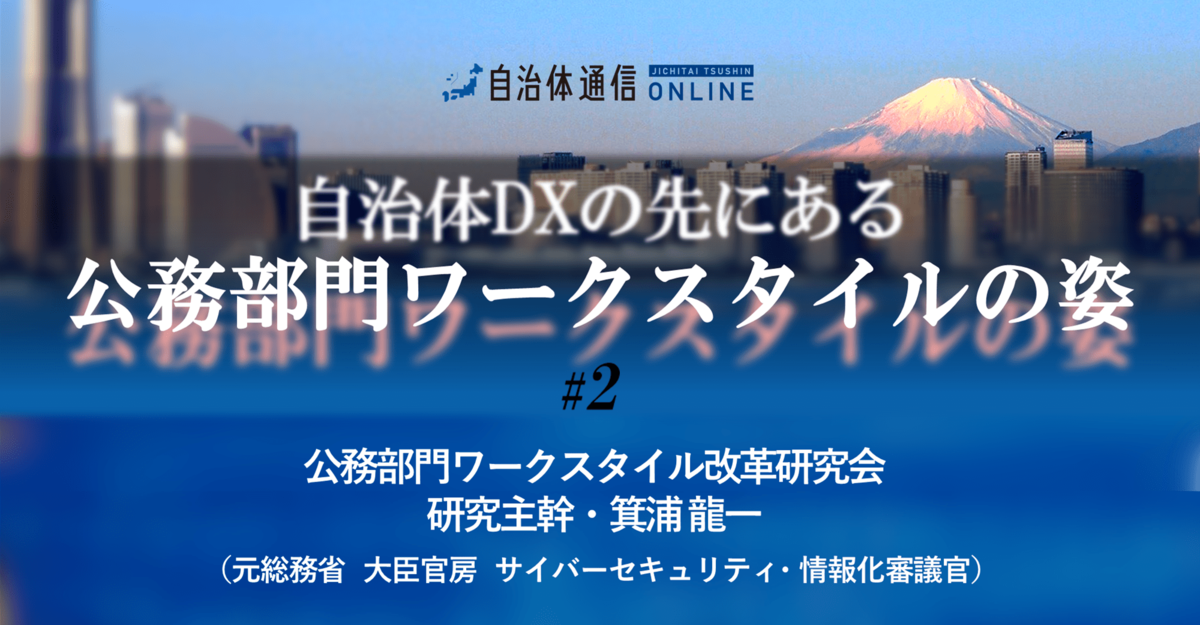
【自治体通信Online 寄稿記事】
自治体DXの先にある公務部門ワークスタイルの姿 #2
(公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹・箕浦 龍一)
自治体DXこそ自治体職員がもっとも本領を発揮できる分野である―。そのワケとは? 公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹(一般財団法人 行政管理研究センター)を務める箕浦 龍一さん(元総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)が自治体DXを進めるうえで最も重要な本質をあぶり出します。
DXとは「デジタル技術の活用」ではない!?
新型コロナウイルス感染症への対応をめぐって、遅れていたDX(デジタル・トランスフォーメーション)が急速に注目され、国や地方の行政においてもDXが最優先の課題のひとつとして浮上しています。長年、電子行政の遅れを嘆いていた識者の間では、これでやっと動き出すのではないか、という期待の声もあがっています。
しかしながら、DXの必要性を指摘する論者や官公庁のDXをサポートすべき立場にあるITベンダーの関係者の中にも、実はDXというものを正しく理解していないのではないか、という向きもあり、不安を感じざるを得ません。
世界で初めてデジタル・トランスフォーメーション(Digital transformation)という言葉を用いたとされるスウェーデンのエリック・ストルターマン(Erik Stolterman)教授は、デジタル・トランスフォーメーションについて、次のように書いています。
“The digital transformation can be understood as the change that the digital technology causes or influences in all aspects of human life.”
(拙訳:デジタル・トランスフォーメーションは、デジタル技術が起因し、又は影響を与える私たち人間の生活のあらゆる局面における変化と理解することができるのだ。)
ここで読み取るべきは、ストルターマン教授がデジタル・トランスフォーメーションの言葉に込めた意味は、「デジタル技術を活用すること」ではなく、「デジタル技術の存在や活用を前提とした社会生活のあらゆる面での変化・変革である」、ということだと考えられるのです。
求められているのは現状の「見直し」ではない!?
平成中盤以降から急速に進展したICT技術の進展は、時にICT革命と呼ばれるほどの劇的な変化を社会生活にもたらしたと言われています。確かに私たちの身の回りには最先端のデジタル技術が使われ、行政の様々な業務においてもAIを含めた様々な技術が実装されるに至っています。
しかしながら、従来の既成概念や既往の業務フローがほぼそのままに存置され、その一部にデジタル技術を活用するにとどまった結果、ICT革命後も、押印を必要とする書面手続や窓口業務はそのまま存置されてきたのが実情です。
新型コロナウイルス感染症の問題が発生して以来、「ハンコ」(押印)や「FAX」が悪玉に仕立てられました。でもその結果、押印を廃止して署名に置き換えられたとか、その結果、以前なら社長印の押印でよかったのに社長が長時間不在なので署名をもらうことができず、書類作成に時間がかかるようになったとか、そんな笑い話のようなことが、いまだに一部では発生しているのが実情です。
本当に大事なのは、今あるやり方を「見直す」というアプローチよりも、本来やりたかったこと、目指したかったことにさかのぼって、ゼロからそこにたどり着くためのアプローチを、デザインしなおすこと(リデザイン=再設計)ではないかと思います。
押印(ハンコ)を必要としていた書面は、なぜ必要だったのか。その書面を求めていた手続は、そもそも何のためだったのか。今の技術を前提とすれば、もっとシンプルな業務フローをデザインすることが可能で、そのフローの下では、そもそも当該書面自体が不要ではないのか。そういう考え方やアプローチこそが、トランスフォーメーションを実現するための道だと思います。
行政で有識者会議を開催する際に、委員候補に就任の「承諾書」を求めるという手続きひとつとってみても、巷では、「承諾書に押印は必要ないよね?」という短絡的な議論が聞こえてきますが、そもそも「承諾書」は必要なのでしょうか。そもそもなぜ委員就任に承諾書が必要なのでしょうか? 想像するに、役所の内部での会議開催の意思決定のための決裁書類に、委員委嘱予定の有識者各位から就任の内諾は得ている旨の「証拠書類」として添付しなくてはいけないからではないでしょうか?
だとすれば、委嘱予定の有識者と接触した職員が「〇年〇月〇日に担当者何某が電話(メールor対面)にて委員就任を打診し本人から内諾を得ている」旨の記載を決裁に付記することでなぜ足りないのか、もういち度考え直せばよいのです。

ゼロから目的への到達手段を考えよう
例えてみると、東京から阿蘇まで行かなくてはならない場合の経路の問題を考えてみましょう。明治期までは、街道を歩いていく、馬に乗る、駕籠(かご)を使う、一部経路を船で移動するというような選択肢があったと思います。明治以降、新しい移動手段が生まれ、それまで基本的には徒歩移動していた経路の一部を鉄道で移動するようになり、自動車が使われるようになり、昭和の時代にはこれに航空での移動という選択肢が生まれ、鉄道での移動についても新幹線という高速鉄道が選択肢に加わりました。
これらは、現代でいうところのIT化やデジタル化と近い技術の利活用と考えられます。発想方法も、目的地までの経路の一部をいかにして高速化できるか、という範囲の中での発想だったと考えられます。
これに対して、DX時代の発想方法は、極端な喩(たと)えですが、間もなく実用化される空飛ぶクルマを利用すれば、従来の経路を気にすることなく、ダイレクトに目的地(この例では阿蘇)まで到達することができる、という発想方法です。
この例では、経路が変化したように思われるかもしれませんが、実は、目的に到達するための技術環境が飛躍的に変わったことで、従来の「経路」自体が意味をなさなくなった、という風に捉えることができるのかもしれません。つまり、DX時代の発想方法では、技術をどう利活用するか、という以前に、本来の目的を見据えて、ゼロから到達手段を考えるというアプローチが大事であることがわかります。
自治体職員の本領の見せ時
このようなアプローチを、業務の単位で、そもそも目指すべき成果に向けてデザインしなおすということによって、トランスフォーメーションへの道は開かれます。良く言われる「ゼロ・ベース」の見直しとは、今ある業務フローを前提に要不要を考えるところから始めるのではなく、目的に向けてのリデザイン的なアプローチを意味するのではないかと考えます。結果として、現状と比較すると「思い切った見直し」「ゼロベースの見直し」が実現するのです。
「デジタル・トランスフォーメーション」というと、ITやデジタルに苦手意識を感じたりする方も多いのではないかと思うのですが、実は、その一番重要な本質は、「デジタル」ではなく、技術の飛躍的・革命的な進展を前提としながら、本来目指したい目的や未来に向けて、新しい仕組みや制度を再設計すること。
そのように考えれば、実は、長年地域の仕組みや制度のデザインに携わってきた自治体職員の皆さんの本領が最も発揮しやすい分野ではないかと思うのです。
地方の仕事の中には、国が作る法律・制度の制約の中で処理しなくてはならない業務も多く、自治体だけでは如何ともしがたい、という面もあると思いますが、デジタル庁が創設され、国全体を挙げてDXを進めて行く機運がようやく熟し始めた今だからこそ、各地域の皆さんは、ぜひ本稿で申し上げたような発想方法の転換を心がけて、地域のDXを進める一歩を踏み出していただき、国での改革が必要な分野に関しては、ぜひ、現場から声を上げていただきたいと思います。
自治体通信への取材依頼はこちら
箕浦 龍一(みのうら りゅういち)さんのプロフィール
公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹(一般財団法人 行政管理研究センター)
元総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
総務省 行政管理局時代に取り組んだオフィス改革を中心とする働き方改革の取組は、人事院総裁賞を受賞(両陛下に拝謁)。中央省庁初の基礎自治体との短期交換留学も実現するなど若手人材育成にも取り組む。
官僚時代から、働き方、テレワーク、食と医療など、さまざまなプロジェクト・コミュニティに参画。
2021年7月に退官。一般社団法人 日本ワーケーション協会特別顧問、一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム理事も務める。2021年9月に、一般財団法人 地域活性化センターの人材開発シニアフェローに就任。
<連絡先>ryuichi.minoura.wkst@gmail.com
(@を半角にしてください)