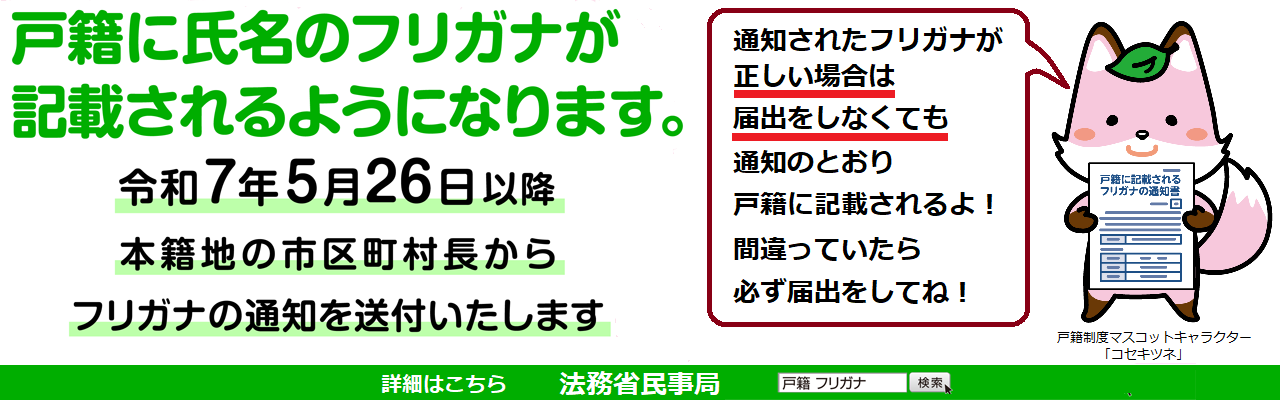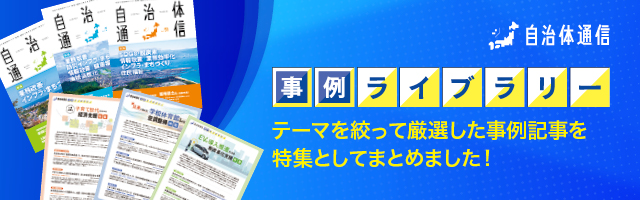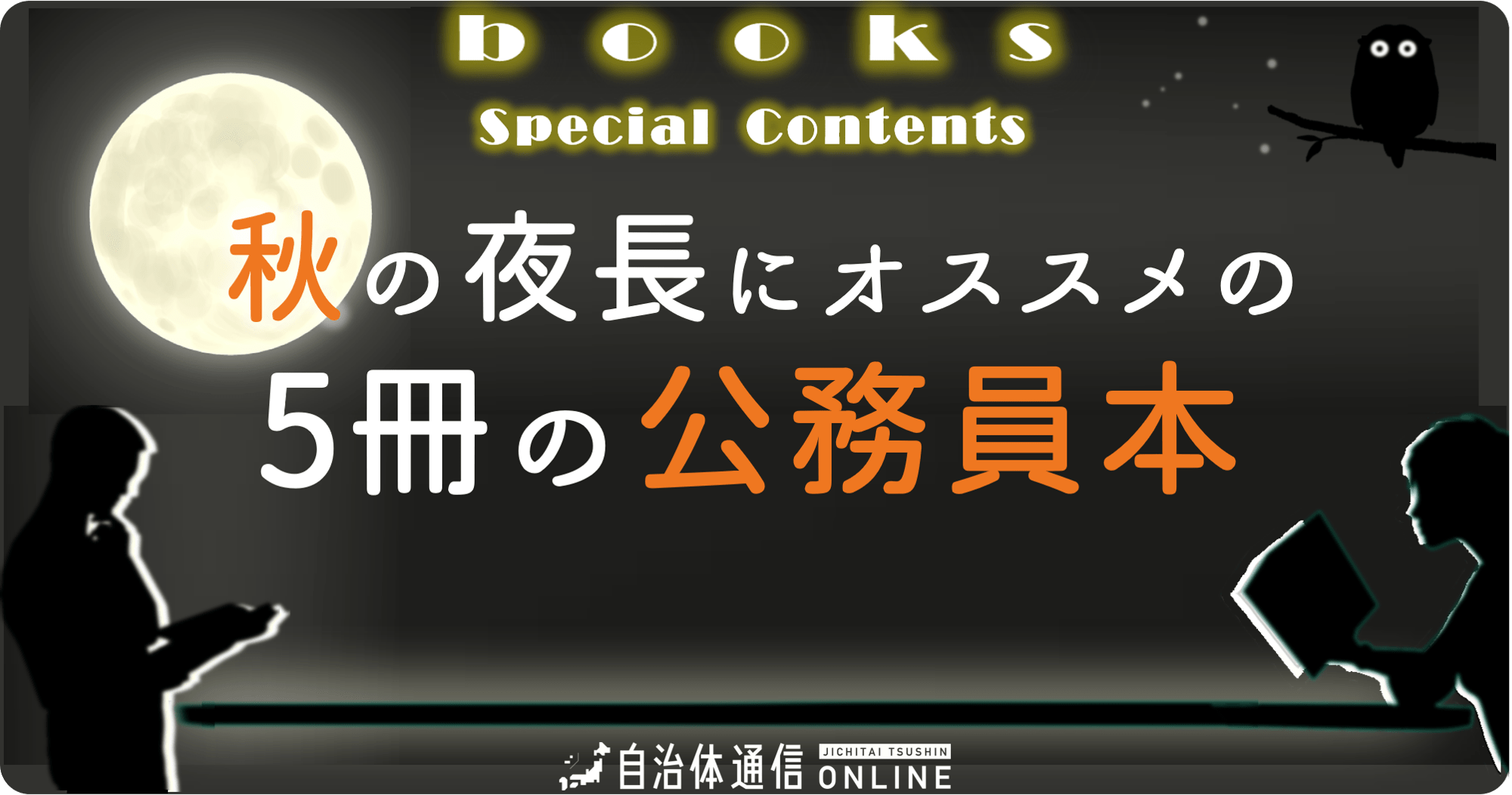
居座っていた厳しい残暑も過ぎ、「読書の秋」が今年もやってきました。そこで、秋の夜長にじっくり向き合いたい、5冊の公務員本をご紹介します。(肩書は記事公開当時)
全体最適の視点で効果を上げる 自治体DXの進め方
髙橋 邦夫(地域情報化アドバイザー/合同会社 KUコンサルティング 代表社員/豊島区 元CISO)
《記事の要約》
自治体の改革支援の経験は、デジタルに限らずさまざまな分野で活かせることを実感するとともに、今後は「エバンジェリスト(伝道師)」として次の世代に引き継ぎたいと思い、2冊目の著書となる本書『全体最適の視点で効果を上げる 自治体DXの進め方~推進段階別の課題と対応~』(第一法規)の執筆に取り組みました。
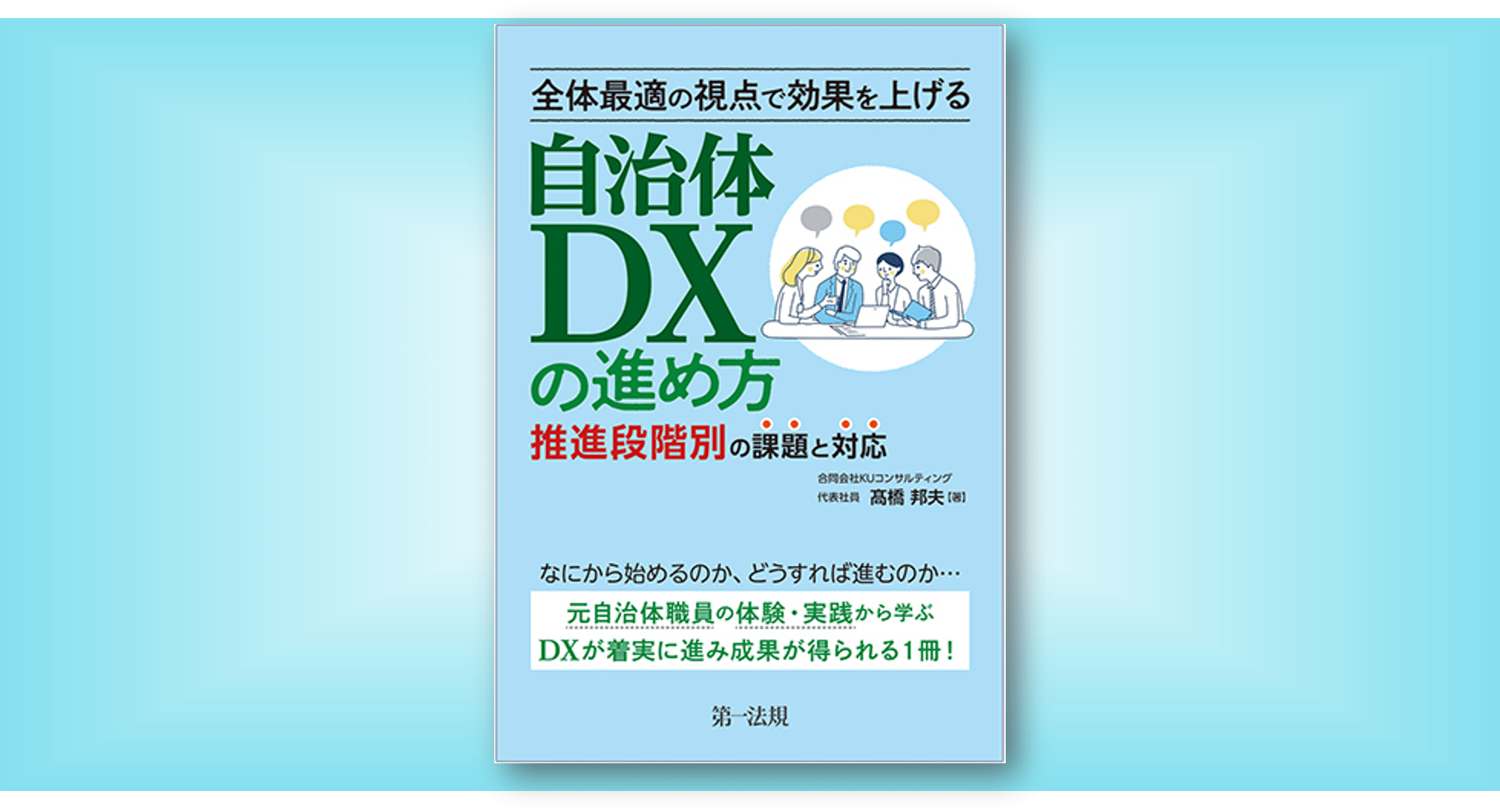
『全体最適の視点で効果を上げる 自治体DXの進め方~推進段階別の課題と対応~』(第一法規)の表紙カバー
自治体がデジタルを活用した新たな行政サービスを見出すためには、総務省が進める地域情報化だけでなく、経済産業省のキャッシュレス化や厚生労働省のテレワーク、文部科学省のGIGAスクール構想など複数の省庁が進める施策に目を配る必要があり、そのことによって現在デジタル庁が取り組んでいるデータ連携・データ活用へと発展していくことを、身をもって体験してきました。
デジタル化を進めるにはさまざまな障壁や課題を乗り越える必要があります。本書を手に取っていただくことが、その一助となることを願うとともに、障壁や課題を乗り越えた経験を次のライフステージに活かしてもらいたいと思っています。
「なぜ?」からわかる地方自治のなるほど・たとえば・これ大事
塩浜 克也(佐倉市 職員)/米津 孝成(市川市 職員)
《記事の要約》
本書『「なぜ?」からわかる地方自治のなるほど・たとえば・これ大事』(公職研)の著者は、千葉県の佐倉市役所と市川市役所の現役の職員です。それぞれの役所において、法規部門への所属を経験し、これまでも共著で若手職員向けの参考書(学陽書房刊『疑問をほどいて失敗をなくす 公務員の仕事の授業』)を執筆するなど、後進の応援に努めてきました。
(参照記事:「疑問をほどいて失敗をなくす 公務員の仕事の授業」)
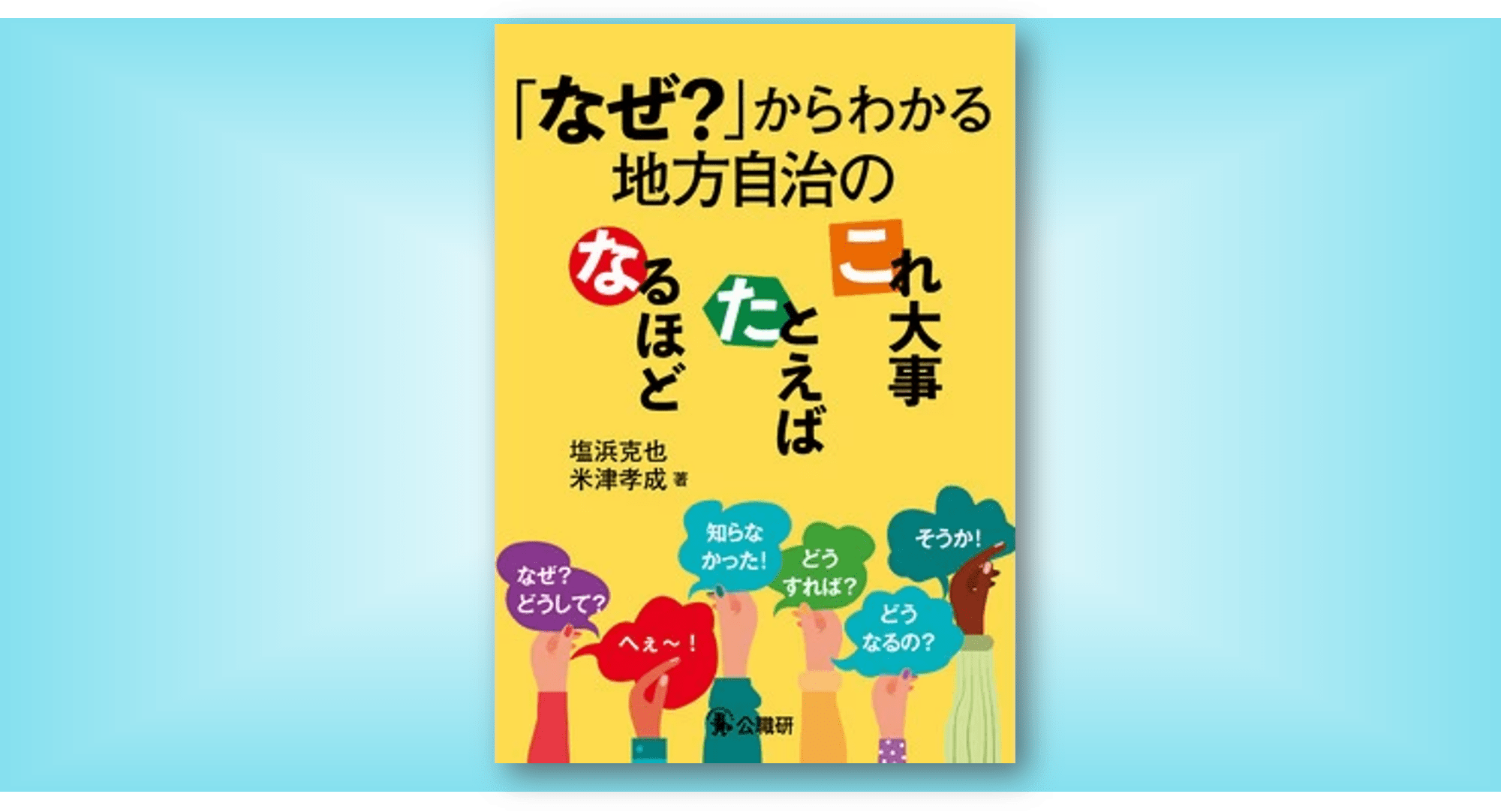
『「なぜ?」からわかる地方自治のなるほど・たとえば・これ大事』(公職研)の表紙カバー
地方自治制度のどこから手を付けていいかわからない。そんな方は、本書を是非手に取ってみてください。具体的な事例によるイメージの喚起で、知識の習得は楽になるはずです。
ベテラン職員の方にも、本書は知識の確認のお役に立てるものと考えます。苦手な分野を見つける契機にもなるでしょう。
職員研修の講師を務める機会がある職員の方は、この本から講義の「ネタ」を仕入れてください。聴衆の皆さんの理解を深める材料になればと思います。
本書を読んだ方々が「地方自治って、おもしろい!」と感じていただけたら幸いですし、ひいては、皆さんのお仕事を通じ、地域の方々の暮らしの安心と充実につながれば、著者としてこれに勝る喜びはありません。
これだけは知っておきたい! 技術系公務員の教科書
橋本 隆(伊勢崎市 建設部 土木課長)
《記事の要約》
本書『これだけは知っておきたい! 技術系公務員の教科書』(学陽書房)では、土木職や建築職が多く在籍する職場で活躍する技術職の公務員の皆さんのことを「技術系公務員」と呼ぶことにしました。
すでに技術系公務員の管理職として3年目を迎えていた私は、現職の技術系公務員だけでなく、学生や社会人から技術系公務員になったばかりの新規採用職員に向けた実務書の必要性を強く感じていました。
将来、さらに技術系公務員の人員減が進む可能性が高い中で、「技術系公務員でよかったです」「技術系公務員のやりがいを感じています」「技術系公務員として豊かな人生を送っています」と語る人が増えてくれることを心の底から望んでいたからです。
技術系公務員向けのわかりやすい教科書があったらとのシンプルな想い。それこそが本書を書くことになったきっかけです。
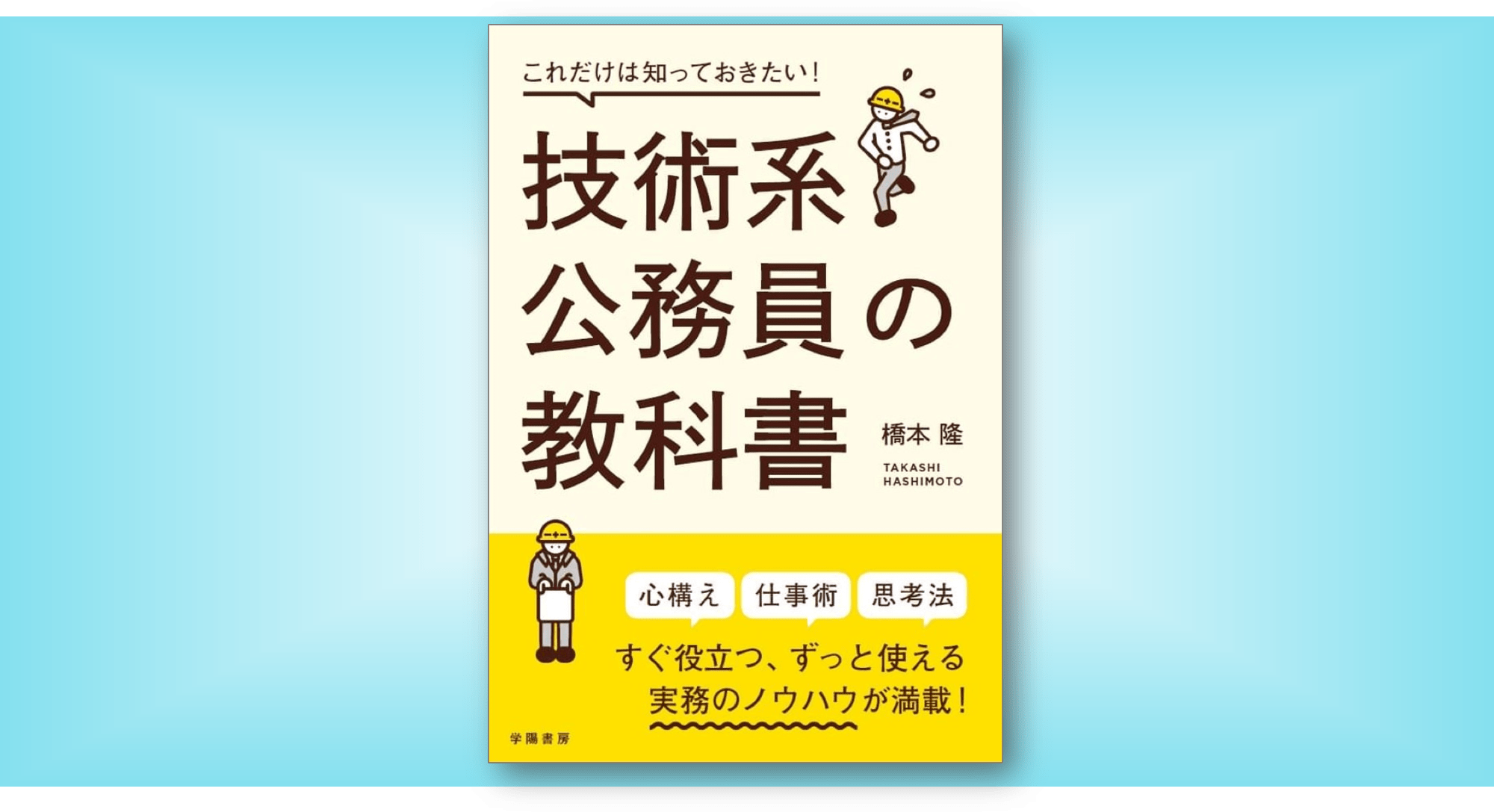
『これだけは知っておきたい! 技術系公務員の教科書』(学陽書房)の表紙カバー
今後も、技術系公務員を取り巻く状況は大きく変化していくでしょう。こうした新しい変化にも対応できる技術系公務員になるためにどのような視点を身に付けておくべきか、本書にはそのヒントをたくさん盛り込みました。こうしたヒントは、土木職や建築職ではない技術職にも通ずる仕事の要諦として、広くお役立ていただけたら幸いです。そして本書が、技術系公務員の皆さんにとって「座右の書」になれば、これに勝る喜びはありません。
自治体のふるさと納税担当になったら読む本
林 博司(パブリシンク株式会社代表取締役/合同会社LOCUS BRiDGE 共同代表/北本市 元職員)
《記事の要約》
本書『自治体のふるさと納税担当になったら読む本』(共著、学陽書房)を読んでいただければ、ふるさと納税制度全般、これまでの制度の変遷、業務の内容や改善方法・スケジュール、効果的なプロモーション、寄附金の使い道、ふるさと納税に関わる全国の素晴らしい事例を知ることができ、ふるさと納税という特殊な業務のポジティブな可能性を大いに感じていただくことができるはずです。
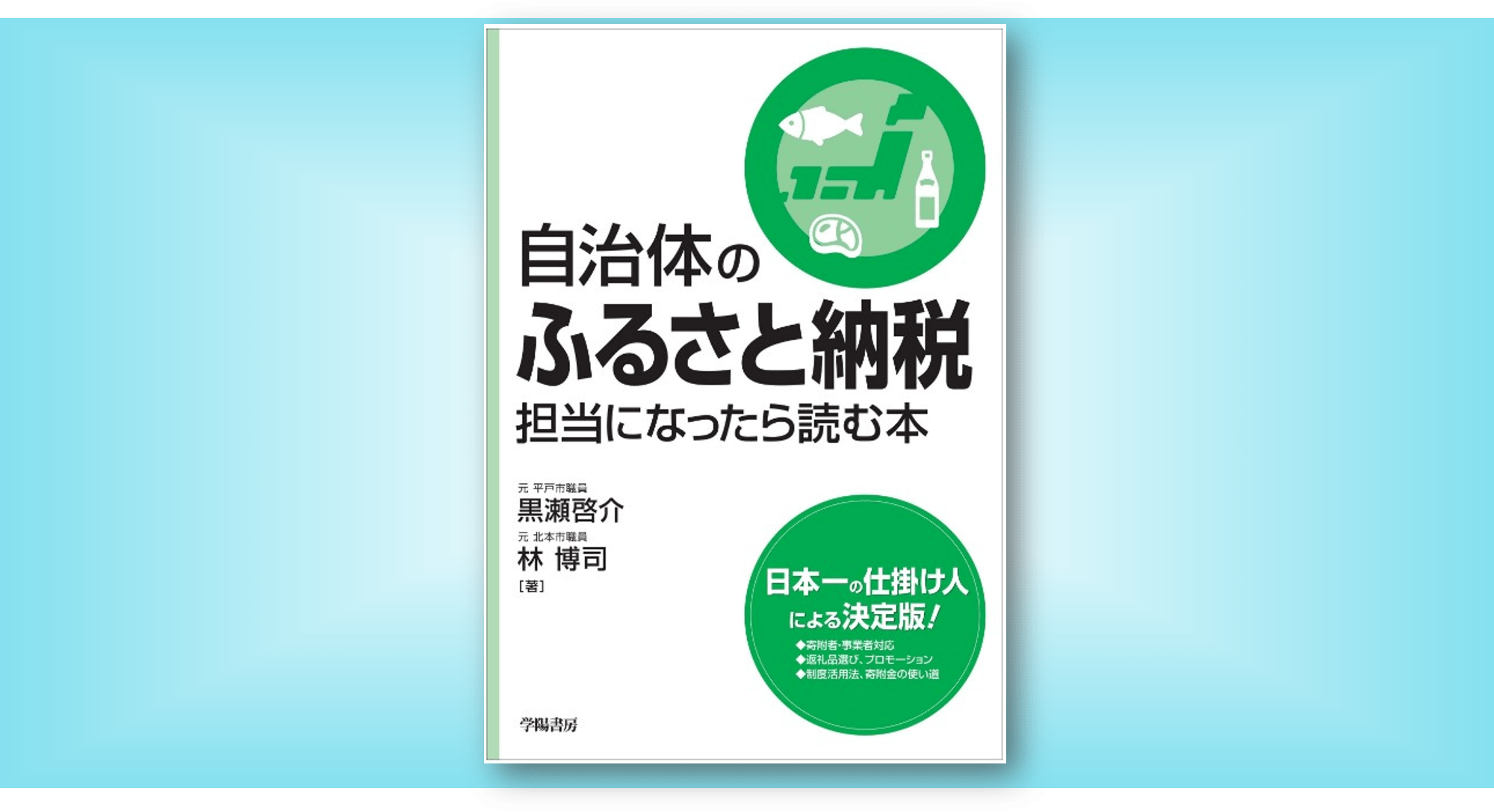
『自治体のふるさと納税担当になったら読む本』(学陽書房)の表紙カバー
最初からある程度、制度に関する知識や業務ノウハウを知っていることができれば、苦しみ・諦めるフェーズからいち早く抜け出し、ふるさと納税のポジティブな面を活用して、自分のまちや事業者に“光”を届けることができる。そのような想いから今回自治体ふるさと納税担当者向けた本を執筆する機会を頂きました。
少しでも多くのふるさと納税関係者に手に取っていただき、この制度が誰からも愛され、日本全体に光を当てる制度になっていくことを心から願います。
自治体職員の「自治体政策研究」史~松下圭一と多摩の研究会
小関 一史(東松山市 職員)
《記事の要約》
本書『自治体職員の「自治体政策研究」史~松下圭一と多摩の研究会』(公人の友社)では、当時と現代の「自主研究グループ活動の環境の違い・共通点」のほか、「なぜ、自主研究活動は発生したのか」、「なぜ、地方自治の研究分野が確立されていない時代に、行政学者が自治体職員と連携したのか」、「自主研究グループ活動が学会設立に動き出した場面」、「自主研究活動の阻害要因」などについても注目をしました。

『自治体職員の「自治体政策研究」史~松下圭一と多摩の研究会』(公人の友社)の表紙カバー
第一次自主研ブームを活動した方々が定年退職を迎える頃、第二次自主研ブーム世代が入庁しました。入れ違いで退職をしていった先輩たちの世代は、まだ自治体が全国的なイベントなどを開かなかった時代の1984年に、全国自主研究交流シンポジウムを中野サンプラザで開催しています。その後も、通信手段が電話と手紙だった時代に全国集会を開催した熱意と熱量、突破力を感じ取っていただけたら、今の自主研活動に新鮮な視座が加わるかもしれません。
本書は、法政大学大学院公共政策研究科へ提出した修士論文を基に、大幅に加筆修正を加えたものです。学術論文にはとっつき難い感があるかもしれませんが、「秘密結社」「コミケ」「よんなな会」や、第一次世代へのインタビューの掲載、関東地方の自主研究グループ活動の火付け役となった、第1回関東自主研サミットの会場の関係など、懐古主義的ではない読みやすい内容になっています。現在(第二次自主研ブーム)と過去(第一次自主研ブーム)を対比して読むことで、今、運営や参加をしている自主研究グループへの想いを深めていただくきっかけになれば幸いです。