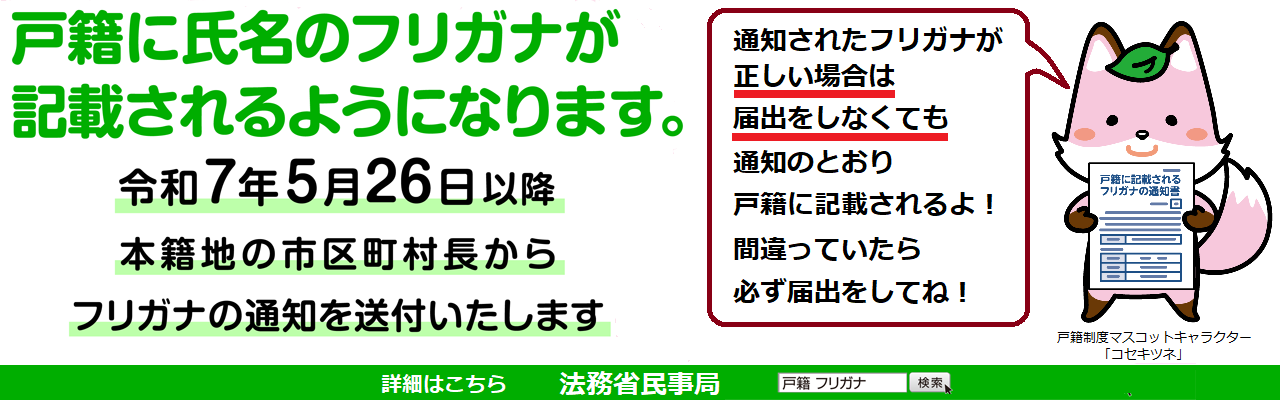ふるさと納税の寄附増のカギは、工夫を凝らしたPR活動にあり

ふるさと納税制度が開始されて早17年が経ちました。総務省の調査によれば、令和5年度の寄附総額は全国で1兆円を超え、いまや地方部の自治体にとっては貴重な財源となっており、その寄附金によって多様な住民サービスが支えられています。その一方で、数十万の返礼品があるなか、ほとんどのPR活動はポータルサイトに限定されており、認知度の低い自治体は寄附が伸び悩んでいるそうです。こうした苦境からの脱却を試みるため、民間企業と協力して取り組んだ先進事例を紹介します。
ふるさと納税を取り巻く現況
ふるさと納税は、国民が「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として平成20年に創設されました。「納税」という名称がついてはいますが、実際には国民が自由に自治体に「寄附」できる制度です。
こうした「寄附」に対して、自治体が「御礼」として配布するのが返礼品です。この返礼品は、自治体が予算を設けて、地元の名産品などを調達します。そのため、魅力ある地場産品が豊富な自治体ほど、寄附総額が高くなる傾向があります。令和5年度の寄附受入額実績によれば、トップは北海道で、次いで福岡県、宮崎県と続きます。
【都道府県別寄附受入額トップ5】
1位 北海道 1,654億9,600万円
2位 福岡県 615億400万円
3位 宮崎県 520億1,200万円
4位 静岡県 457億5,100万円
5位 鹿児島県 443億2,900万円
このように、トップ5には有名な特産品が豊富にある都道府県が名を連ねています。一方で、認知度があまり高くなかったり、目立った特産品がなかったりする自治体で寄附が伸び悩んだことで、自治体間の「ふるさと納税格差」が生じ、平成年代は自由競争の様相を呈していました。
制度の規制強化で生じる懸念
ふるさと納税の返礼品をめぐる競争が激化したことで、返礼品に地元と関連性の薄いギフトカードなどを調達する自治体もありました。こうした競争に「待った」をかけたのが、総務省です。令和元年には返礼品の規制を次のように強化しました。
【令和元年の返礼品規制】
●返礼品は地場産の品物に限り、価格は寄付金額の3割程度にする
●返礼品の価格やその割合の表示を行わない
●商品券・電子マネーなど金銭に変わるものや資産性の高い品物(貴金属・宝飾品・電子機器)は返礼品にしない
これによって、自治体によっては返礼品の見直しを行わざるを得なくなり、方針の変更を余儀なくされました。そのなかで新たな問題が発生。新たに問題視されたのが、自治体が寄附を受けた後にかかる「隠れ経費」の増大です。本来、返礼品にかかる経費は「寄附総額の5割未満」というルールが設けられていましたが、寄附を受けたあとの発送料などを計上していない自治体もあったのです。これが問題視され、令和6年10月には、新たに「経費5割未満」の規制が強化され、経費に含まれる項目が明文化されました。
【返礼品の経費に含まれる費用】
●返礼品等の調達費用
●寄附金の受領証の発行事務に要する費用
●ワンストップ特例に関する申請書の受付事務に要する費用
●返礼品を紹介する仲介サイトなどに支払う手数料
これによって、自治体によっては各返礼品の経費が増大し、寄附金額を上げるなどの対応を迫られました。寄附者から見れば「値上げ」に映ることから、寄附の需要がさらに厳しくなっています。
加えて、令和7年10月には、ポータルサイトのポイント付与制度が禁止されます。これらの規制は自治体間の公平性を担保することを目的としていますが、自治体によっては歳入の減少につながり、財源に小さくない影響を及ぼすのではないかと懸念されています。
寄附を伸ばすカギは「PR力」
激しい競争と相次ぐ規制強化のなか、返礼品への寄附を伸ばすカギを握るのが「積極的なPR活動」です。そこで、問題になるのは費用です。広報にかかる費用も「50%未満」の経費に含まれるため、あまり予算をかけられません。
そのため、どれだけ費用を抑えて「PR活動」を行えるかどうかが、ポイントになります。その際、費用対効果の高い活動として、SNS活用があります。地元の有名なインフルエンサーなどに依頼して、SNSで拡散することで、返礼品だけでなく地域の魅力発信にもつながります。
SNSによるPR活動には一定の効果が期待できますが、検索でヒットしないと、ユーザーが閲覧までたどり着けないというデメリットもあります。また、SNSから返礼品のサイトまでうまく誘導できるコンテンツの構成力も試されるため、即効性を期待するのは難しいでしょう。
そこで、有効になるのがポータルサイトにおけるバナー広告の工夫です。民間企業の協力を得て、バナー広告を改善した事例を紹介します。
【伊万里市】ポータルサイトへの掲載を一括委託し、寄附額が約2.3倍に

伊万里焼で知られる伊万里市(佐賀県)では、ふるさと納税の寄附金を子どもの医療費無償化などの重要施策に用いています。また、伊万里牛や伊万里梨などの返礼品も好調で、令和4年度は過去最高の約29億円に達しました。しかし、競争の激化によって翌年度には前年度を下回る結果になってしまったうえ、制度改正による課題も生じていたそうです。
令和4年度までの伊万里市の経費は50%を上回っており、対応に迫られていた。これまで市職員や中間事業者が行っていた返礼品の登録や受発注業務、寄附者からの問い合わせ対応や書類発行業務などにかかる人的・金銭的コストを押し下げる必要があった。 そこで、上記のような業務を一括で請け負ってくれる業者を検討。ふるさと納税のポータルサイトを運営する民間企業に委託することに決定した。 |
|---|
この民間企業のソリューションの大きな特徴は、従来よりも経費が確実に抑えられるうえ、サムネイルやキャッチコピーの改善のほか、自治体職員では思いつかないWebマーケティングの専門的な知見によるページ編集によって、寄附額の増加を図れる点にあります。
伊万里市では、導入直後から効果が表れ、令和6年5月には、寄附額が前年同月比で約2.3倍にも増えました。ふるさと納税の取り組みは、返礼品提供事業者を通じて地域経済へ還元される重要な役割を担っているだけでなく、市の魅力を全国に発信するため、今後も「選ばれる自治体」を目指して取り組みを継続していくと決意を新たにしています。
【恵庭市】バナー広告にタレントを起用し、アクセス数が13倍超に

恵庭市(北海道)は、全国トップクラスの知名度を誇る札幌市、令和5年に新球場『エスコンフィールドHOKKAIDO』がオープンして活況に沸く北広島市に挟まれています。
両市と比較すると、やや認知度が低い恵庭市ですが、有名ビールメーカーの大工場が立地するため、返礼品にはアルコール類をラインナップし、令和4年に至るまで寄附金額も右肩上がりで増えていました。しかし、令和5年の制度改正によって、令和5年には初めて前年割れしてしまったと言います。
恵庭市では、令和5年に寄附総額が前年割れしたことから、経費の1%を予算に回し、PR活動の強化に乗り出した。令和6年度当初は、地元のインフルエンサーを起用したSNS活用などで閲覧数が6万以上に達するなど、効果を感じていたが、寄附金額は依然として伸び悩んでいた。 そこで、需要が増加する年末に向けて、新たなPR活動を模索。民間企業からタレントを起用したバナー広告を提案され、同年11月から有名女性タレントの写真を加えたバナー広告を展開した。 |
|---|
この民間企業のソリューションは、初期費用がかからない定額制で、数百点あるタレントの写真を自由に活用できるというもの。本来、有名タレントを起用すると、撮影などの経費も含めて数千万円というコストがかかります。
さらに、事務所との権利関係の折衝など、慣れない職員にとっては大きな負担になりかねません。そういった細かい業務も一括して、民間企業で請け負っているため、同市職員は「どう写真を活用するか」だけを考えられたといいます。
結果、タレントを起用したバナー広告は、あるポータルサイトで月間アクセス数が13倍超に増加したそうです。
「能動的・受動的」広告の両輪でPR活動を充実
このように、ふるさと納税のPR活動は、コストを抑えつつ多様な「アクセスの入口」を設けることが大切です。SNSのように、ユーザーが「能動的」にアクセスしたくなる仕組みに加え、キャッチコピーなどの編集スキル、タレントの起用など、ぱっと見てわかる「受動的」な広告にも大きな効果があります。
こうした活動の多くは、プロの知見を活用したほうが効果も向上します。当サイトに掲載されている先進事例を参考に、新たなPR活動を模索してみませんか。
【参考】
総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000960670.pdf