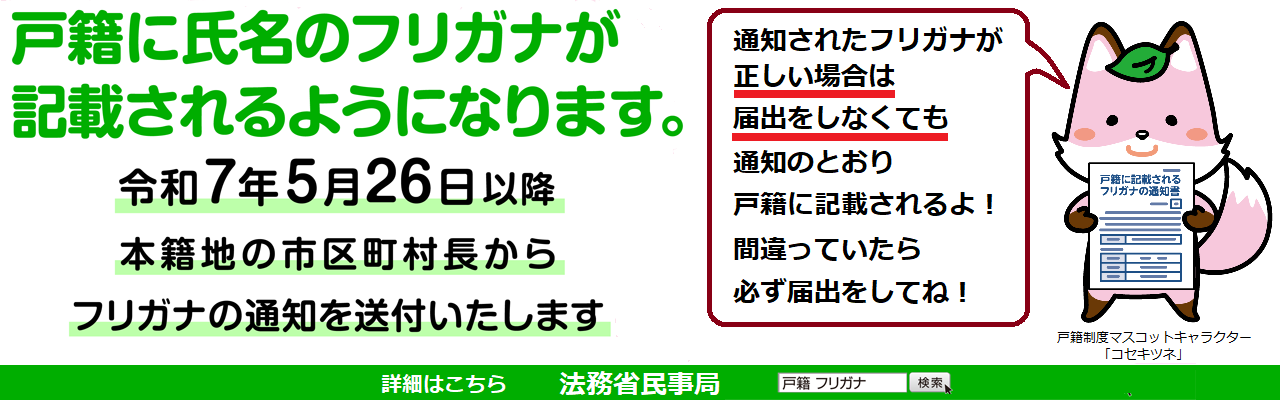窓口業務改革で職員の負荷軽減と住民の利便性向上を実現

少子高齢化・人口減の進展などによる職員の減少を見据え、自治体ではデジタルを活用した業務効率化が喫緊の課題となっています。そのなかで、多くの自治体が推進しているのがデジタル化による「窓口業務改革」です。窓口での問い合わせ対応の多さは、本来の手続き業務を遅滞させる要因のひとつとなり、職員の負荷を増やす原因となっていました。本記事では、窓口業務の効率化によって、自治体職員の業務負荷を軽減するとともに、窓口での手続きにおける住民の負担を減らす取り組み事例を紹介します。
総務省は自治体の窓口改革を後押し
総務省は、行政手続きのオンライン化だけでなく、申請書作成の手間を軽減する「書かない窓口」などを導入し、「住民と行政との接点(フロントヤード)の改革」を進めていく方針です。これにより、住民サービスの利便性向上とともに、自治体職員の業務効率化を図りたい考えです。企画立案や相談対応といった業務への人的資源のシフトを促すことで、持続可能な行政サービスの提供体制を確保していくことが重要としています。
この一環として、同省では、デジタル技術を活用した自治体の窓口改革を後押しする施策を行っています。令和7年1月には、オンライン申請などによる住民の利便性向上と、業務効率化の両立を目指し、窓口業務を含む総合的な改革に取り組む9市町をモデル事業に採択。各自治体に1億2,000万円を上限として支援を行う予定です。
「書かない窓口」に取り組む市区町村は2割
現在、窓口業務などフロントヤードの改革に向けて、自治体はどのような取り組みを行っているのでしょうか。総務省が令和6年4月、全国の自治体を対象に実施・公表したフロントヤード改革の取組状況調査結果(複数回答)は次の通りです。同調査によると、「書かない窓口」の構築に取り組む自治体は、全市区町村の20.9%にとどまっています(指定都市では60%)。
「手続き案内システム」=市区町村:15.9%、指定都市:90%
「AIチャットボット」=市区町村:19.3%、指定都市:60%
「予約システム」=市区町村17.7%、指定都市:70%
「リモート窓口」=市区町村:8.3%、指定都市:25%
「キオスク端末」=市区町村:54.5%、指定都市:85%
「総合案内」=市区町村:55.5%、指定都市:95%
「ワンストップ窓口」=市区町村:28%、指定都市:55%
「書かない窓口」=市区町村:20.9%、指定都市:60%
このうち、「書かない窓口」に取り組んでいる市区町村(363団体)に、その実施方式(複数回答)を聞いたところ、次の結果になりました。
「本人がネットで事前記入」=34.4%
「マイナンバーカードを用いて読み込み入力」=51.2%
「本人が端末(タブレットなど)に入力」=31.7%
「職員が聞き取って端末に入力」=62.3%
「自治体が保有しているデータを表示」=37.7%
「その他」=5.5%
調査結果からは、「書かない窓口」の具体的な実施方式として、職員が住民から必要な情報を聞き取り、それをタブレットなどの端末に入力する形で取り組んでいる自治体が多いことがわかります。しかし、本来の意味で「書かない窓口」が目指すのは、職員の手を借りることなく、住民自身が入力を完結できる仕組みです。現状では、「書かない窓口」に取り組む多くの自治体においても、職員の窓口業務負荷は一定程度残っているのが実情です。
以下からは、窓口業務改革に向けた自治体の先進事例を紹介します。
【袋井市】マイナンバーカードの本人認証で窓口手続きが効率化
袋井市(静岡県)は令和6年から、窓口業務の効率化と住民の利便性向上を目的とした「窓口業務改革」に取り組んでいる。同年4月には、「書かない窓口」や、引っ越しや結婚、出産などの際に必要な手続きをタブレット端末で案内する「手続きナビサービス」を組み合わせたマイナンバーカード利用型の電子申請窓口「らくらくサポート窓口」を支所に開設した。 「らくらくサポート窓口」では、設置されたタブレットなどにマイナンバーカードを認証させることで、引っ越しや結婚、出産などの際に必要な手続きを漏れなく確認できる。また、電子申請では、本人の情報をプリセットし最低限の情報の入力で申請ができるほか、各種証明書の自動交付も可能となる。 窓口に配置されたコンシェルジュ(職員)や、オンラインサポートオペレーターにより、各種手続きにおいて、デジタル・アナログ両面でサポートを受けることができる。マイナンバーカードの認証により、住民のスマートフォンなどでも電子申請が可能となることで、「書かない」さらには「行かない」市役所につなげたい考えだ。 |
|---|
袋井市が構築したのはマイナンバーカードを活用した行政窓口の仕組みです。同市が目指す「窓口業務改革」はおもに2つ。1つ目は、住民に対する「申請手続きの案内」の省力化です。住民には、窓口に設置している案内システムの画面で引っ越しなどのライフイベントを選択してもらい、手続き案内を行いますが、その際、マイナンバーカードによる本人認証を行ったうえで案内を進めます。住民は、最小限の設問に答えるだけで、必要な手続きが漏れなく案内されます。
2つ目は「書かない窓口」に向けた取り組みです。ここでは、マイナンバーカードを活用して、市の基幹システムの本人情報を自治体基盤クラウドシステム(BCL)に連携し活用している点が特徴です。申請手続きの際に、マイナンバーカードを活用することで、マイナンバーに紐づく情報が申請フォームに自動転記されます。たとえば、転入者が「案内システム」を利用した場合、システムがマイナンバーに紐づく情報から子どもの有無を判断し、「児童手当の申請手続き」も自動で案内します。こうした仕組みを活用して、設置したのが「らくらくサポート窓口」です。この窓口ではデジタルに不慣れな住民でも安心して利用できるよう、申請相談や申請サポートを行うコンシェルジュを設置しました。必要な手続きを案内したり、電子申請の入力を補助したりするなど丁寧に電子申請のサポートを行っています。
さらに、袋井市では、この仕組みによって、「行かない窓口」も実現するとしています。今回の仕組みは、国が用意するマイナポータル連携を活用することで、インターネット経由で使える設計です。そのため、住民は自宅や外出先のスマートフォンやパソコンからでも、システム構築した一部の手続きはマイナンバーカードを活用すれば、最小限の入力だけで、簡単に電子申請を行えます。
同市の担当者は、マイナンバーカードを活用した手続きの電子化で、手続きにかかる時間が短縮され、窓口がもっと便利になるよう取り組むとしています。こうした窓口改革を積極的に進めて一歩先を行く「行政窓口」を住民に提供したい考えです。
【八戸市】「書かない」「待たない」「行かない」を同時に実現
八戸市(青森県)は、令和5年に「八戸市デジタル推進計画」を策定し、限られた数の職員でも行政サービスの質を担保するための業務改革を進めてきた。その際、重要視してきた業務が、市役所業務の根幹をなす「窓口業務」。手続きによっては、何枚もの申請書へ同じ内容を繰り返し記入する負担やその処理は住民、職員双方にとって大きな負担だった。そこで「書かない窓口」の実現はその解決策になると考えたという。 ただ、人口20万人を超える中核市となると住民の事情やニーズもさまざまで、その対応で職員の負担が増すようでは本末転倒となる。そこで、住民の利便性向上と職員の負担軽減を両立する方法として考案したのが、「書かない」「待たない」「行かない」窓口だった。
「書かない」「待たない」「行かない」の3つの運用が互いにリンクし、同時に行える仕組みとして、民間事業者の「デジタル申請サービス」を導入した。この時期、総務省が募集していた「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」もこの「3パターンでの運用」が条件になっていたことから、同事業にも応募し採択されている。 |
|---|
八戸市では、地元企業の支援でシステム導入を進め、「はちのへスマート窓口」として、本庁のほか市内11のサービスセンターなどで令和6年11月から一斉に運用を開始しました。対象は7課の計132手続きに広げており、同市の担当者は「当初から大規模に開始することを意識した」といいます。一部の手続きのみに適用しても住民利便性や業務改善への寄与は小さいと考えたからです。
導入後、運用から約1ヵ月で約1.6万件の手続きを処理しました。今後は市全体の手続きの約40%をデジタル化するのが目標です。住民からの不満は寄せられておらず、業務改善効果も大きいと評判とのことです。
【大阪市浪速区】BPOの活用で安定した窓口運営が実現
大阪市浪速区(大阪府)は外国人住民の数が同市内で3番目に多く、区役所近辺には複数の日本語学校が立ち並ぶ。普段、来庁者の半数ほどは外国人住民が占めるといい、窓口業務には、中国語やベトナム語など多言語での対応が求められるほかにも、特有の課題が多いという。 たとえば、日本語学校の入学シーズンは、住民登録を行う外国人が数十人規模で一度に窓口を訪れるため、業務の逼迫が起こりやすい。また、戸籍制度の有無や、身分証明書の種類が国によって異なるため、事務手続き上の判断も複雑になる。こうした状況のなかでも住民サービスの質の安定を図るため、同区は「住民情報業務等窓口」を民間事業者に委託している。 |
|---|
現在、多くの自治体は窓口業務のデジタル化を推進し、住民サービスの向上に努めています。しかし、その過程では、職員がデジタル化による恩恵を十分に享受できず、一時的な業務負担の増大が生じているという「過渡期」ならではの課題が生じているケースも少なくないようです。住民サービスの質を維持しつつ、窓口業務のさらなるデジタル化を進めるには、BPOの活用が有効な選択肢になりうるといえます。
大阪市浪速区では、民間委託によって、年間を通じて安定した窓口運営を実現しました。受託した民間事業者によると、同社は人材を定着させる取り組みにより、大阪エリアでは5年以上継続勤務しているスタッフが全体の7割を占めています。そのため同区では、自治体業務に精通したスタッフによる支援はもとより、外国人住民が多いという地域特性に合った支援が、安定した窓口運営につながっているようです。
具体的には、外国語を話せるスタッフ陣を常時、配置しているほか、繁忙期には日本語学校の生徒向けに専用の臨時窓口や順路を用意。ほかの来庁者の窓口対応が滞ることのないよう工夫を行っています。こうした地域特性に合った窓口業務へのBPOの活用によって、来庁者の満足度調査では、「満足」の比率が「90%以上」と高水準が続いているとのことです。

AIが来庁者をサポート
上記で紹介した事例以外にも、窓口業務改革のさまざまな取り組みが全国の自治体で行われています。たとえば、河内長野市(大阪府)では、「窓口予約システム」を導入することで、手続きの事前把握や所要時間の可視化を図るとともに、一時的な集中を避けることで効率的な人員配置を可能にしています。また、申請書の作成を、生成AIを活用したアバターが支援するなど、来庁者のサポートにAIを積極的に取り入れることで、記載台や待合スペースの削減にもつながっています。
個別ツールの導入にとどまらず、住民サービスの利便性向上と業務の効率化を進め、企画立案や相談対応といった職員が注力すべき業務へ人的資源のシフトを促し、持続可能な行政サービスの提供体制を確保していくことが窓口業務改革にとって重要な視点といえます。
人口減に伴い地方公務員の数が不足するなかで公共サービスの水準を保つには、自治体の業務改革が欠かせません。職員の業務負担を軽減しつつ、多様なニーズを持った住民の利便性向上を同時に達成するための取り組みが全国で進んでいます。
【参考】
総務省「令和6年度自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」
https://www.soumu.go.jp/iken/fymodelr6.html
総務省「⾃治体DX・情報化推進概要〜令和5年度地⽅公共団体における⾏政情報化の推進状況調査の取りまとめ結果」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944041.pdf