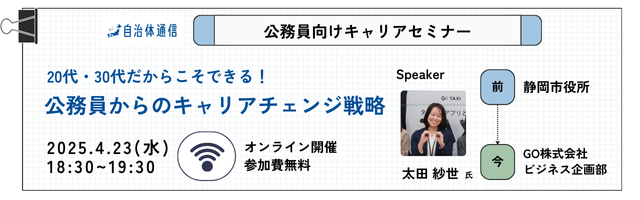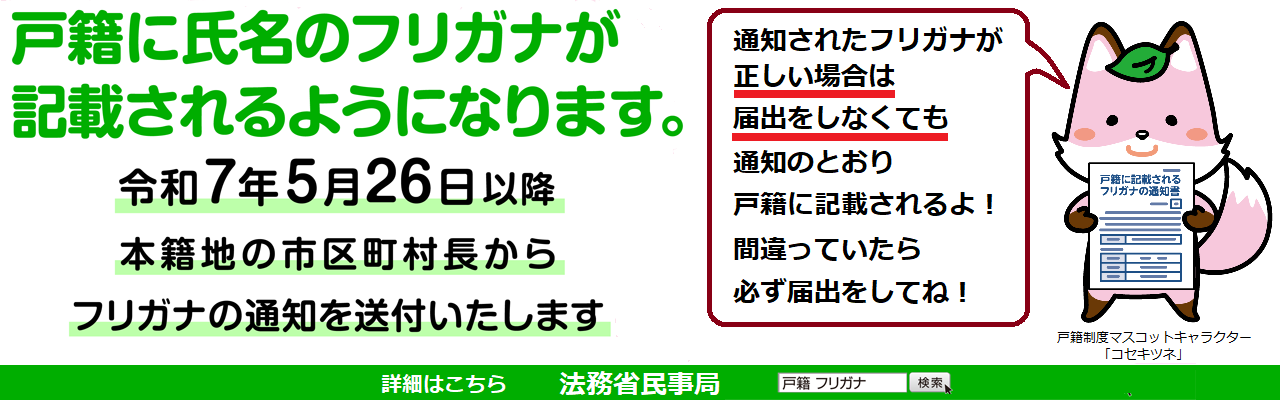《東京都 副知事×三重県 CDO PART3》住民の幸福に貢献する「デジタル社会」の実現

【自治体通信Online Interview】
なぜ私たちは「デジタル社会」の実現を目指すのか #3(聞き手・三重県 田中CDO)
確信に変わったある気づき
三重県CDO 田中(以下、T)
これまで、東京都のデジタル人材育成と変革マインドの醸成や、デジタルツインによる全体を俯瞰した政策立案など、具体的な政策についてお話を伺ってきました(参照記事:#1「“喉の渇き”がデジタル変革を加速させる」、#2「デジタルツインで全体を俯瞰した政策立案を」)。
ここからは、副知事にご就任されて2年半が経過した今だからこその気付きや、今後のビジョンなどについてお伺いします。
まずは、今だからこその気付きについてはいかがですか?

東京都副知事 宮坂(以下、M)
#1の人材育成の文脈でも触れましたが(参照記事:#1「“喉の渇き”がデジタル変革を加速させる」)、やはり都民の皆さんの期待値は「難しいことよりも、早く利便性の高いWeb1.0を実現して欲しい」ということだという気付きがありますね。「Society5.0とかよくわからないけど、それよりもオンラインで行政手続きができないのか」「ホームページで、情報がどこにあるのかわからないのを何とかしてよ」といったことなのだろうと思います。
ですから、まずは地道に、ちゃんと使えるホームページをつくるとか、オンラインで手続きできるといったことを、しっかりとやらないといけないと思っています。
日本の多くの自治体では、ホームページのサイト内の検索機能が不便な状態であることが多いですよね。東京都でも同様の状態です。このサイト内で情報を探す機能を向上させるだけで、都民の皆さんに便利さを実感していただきやすくなるはずだと思いますので、足元から1歩1歩しっかり取り組んでいく必要があります。
T
ホームページと一概に言っても、各局にまたがってそれぞれが膨大な量の情報を管理しているわけですので、その改善に取り組むのは難易度が高い業務となりますよね。
もはやどこから手をつけたら良いのかわからないといった自治体も多いと思うのですが、東京都ではどういったことから取り組まれていますか?
M
東京都では、昨年度からホームページにアクセス解析ツールを導入し、ユーザー数やサイトへの流入経路、デバイスの比率などが把握できるようになりました。それによって気付きが確信に変わりました。
行政のデジタル推進といえば、メタバースや行政手続きのデジタル化、そしてMaaS(Mobility as a Service=移動のサービス化)のような先端技術のイメージもありますが、最も利用されている東京都のデジタルサービスは、結局、「ホームページで情報を探す」ということなのです。
ですから、都民の皆さんの最も大きなニーズは「ホームページで情報をちゃんと探せるようにして欲しい」ということではないかと思うのです。そして、更にデジタルに慣れている人は「申込みもデジタルで」というニーズをもっていることと思っています。
そういった現状を踏まえると、まずは利便性の高いWeb1.0の実現に向けて、検索したら適切な情報にアクセスできるとか、カテゴリーを辿って必要な情報に到達できるとか、基本的なところから1つ1つ利便性を高めていけるといいなと思います。

T
まずは現状を定量・定性の両面から正しく把握する。そのために継続して計測する。そして検証し、改善する。民間では当たり前のことではあるのですが、なかなか多くの自治体でも出来ていないのではないでしょうか。ユーザーテストなども組み合わせて、まずはこれを仕組み化することからスタートしなければ、ですね。
また、膨大な量の情報を徹底的に整理して、簡単に検索できるようなシンプルで使いやすいホームページに進化させることは、全国の自治体が取り組まなければならない重要なテーマですよね。
M
そうですね。東京都以外の自治体でも、「利便性の高いWeb1.0のホームページを実現して欲しい」「情報を簡単に検索できるようにして欲しい」というのは、最大のニーズなのだろうと思います。当たり前すぎて、利用者は言葉にしないだけで。
自治体は組織として技術に強い!
T
それでは、今後のビジョンについてもお伺いしたいと思います。
東京都は17万人を超える職員数と巨大な組織なわけですが、組織の変革に関するビジョンは、どのように描いていますか?
M
都道府県などの広域自治体は、水道や道路といった都市インフラを支えているため、エンジニア(技師)も数多く在籍しています。本質的な組織文化のカルチャーとしては「エンジニアリング・カルチャー」だと思うのですよね。水道や道路などは世界的にも品質を高く評価されていて、毎日、何不自由なく水道や道路を利用できているというのは、まさに組織として「技術に強い」ということなのです。
しかし、デジタルだけ上手くいっていなかった。なぜかと言うと、1つはエンジニアの人数が全く違うのです。水道や道路にはエンジニアが沢山いますが、デジタルは非常に少なかった。私が着任した2年半前は、デジタルのエンジニアは10名ほどでした。今は120名ほどに増えましたが、それでもまだまだ足りないと思います。

水道でも道路でも、様々な業務を民間企業などに委託をしますが、「わかっている人がわかっている人と仕事をするとイイものができる」という成功パターンですから、それはもちろんデジタルでも同じことが言えるはずです。
ですから、あらゆる職員が「技術に強い」組織であるという自信や誇りを持って、他のインフラと同じように果敢に「デジタル社会」の実現に取り組んでいく、それが組織の変革に関するビジョンですね。
T
たしかに、そもそも自治体は「技術に強い」組織であるはずなのですよね。デジタルは21世紀の基幹インフラなので、水道・道路など他のインフラに匹敵するぐらいの人数を確保することは、とても重要だと思います。
やはり、組織の変革で目指すべきビジョンは、住民の皆さんだけでなく職員1人ひとりの自信や誇り、1人ひとりのやり甲斐やウェルビーイングの向上ということになるのですよね。
三重県の「あったかいDX」でも、1人ひとりの自己実現こそが変革で目指す理想状態であるとしていますので、とても共感できます。

「並ばない役所」は実現できる
T
ところで、組織の変革だけに限らず、もう少し拡げて東京都の未来に向けたビジョンとしては、どのように描いてますか?
M
東京都の未来という意味では、究極のビジョンは、都民の皆さんの幸福に貢献する「デジタル社会」を実現するということですね。ただ、その中で自分が直接的に、当面やっていかなければいけないのは、社会から「不便をなくす」ことです。身近な不便を1つ1つ無くしていき、いち早く都民の皆さんに便利さを実感していただきたいと思っていますし、絶対できると思っています。
不便の事例として「行列に並ぶ」があります。昔はゲームソフトも電車の切符も何もかも並んでいました。でも、今の時代で窓口に並んでいるのって、金融機関と病院とラーメン屋と行政ぐらいではないかと。でも最近は、金融機関や病院も並ばなくなってきていますし、ラーメン屋はマーケティングとして意図的に並ばせていたりもするので、そうなるといよいよ最後に残る行列は行政ぐらいしかないということになりかねないですよね。
そんな不名誉な文化遺産になるわけにはいかないので、「並ばない役所」になるというのは目指すべき姿だと思います。バーチャルだけでなくリアルな窓口も裏側は全てデジタル化されているわけですので、予約システムなどと連携して「並ばない役所」は十分に実現可能なのです。

T
住民の幸福に貢献する「デジタル社会」の実現は、国が掲げる「デジタル田園都市国家構想」が目指すウェルビーイング・イノベーション・サスティナビリティにも通ずるところがありますね。組織でも社会でも、1人ひとりの幸福に向き合うことが変革を推進する上で、とても重要なのだと強く共感しました。
最後になりますが、この対談は、是非とも全国の自治体の変革推進担当者の皆さんに読んでいただきたいほどに、とても学びの深い対談となりました。本当にありがとうございました!
M
こうやって、変革に取り組んでいる者同士で失敗も成功もナレッジを共有できると良いですよね。
こちらこそ有意義な対談の機会をいただき、ありがとうございました!
(終わり)
自治体通信への取材のご依頼はこちら
東京都副知事 宮坂 学(みやさか まなぶ)さんのプロフィール
デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出し、都民が質の高い生活を送ることができる東京版Society 5.0「スマート東京」の実現に向け、デジタルに関連する様々な施策を推進。
IT大手・ヤフー株式会社に20年以上勤務し、会長職を務めるなど、企業経営者として経験を積み、ヤフー退社後、2019年7月に東京都参与に就任。世界最高のモバイルインターネット網の建設を目標とする「TOKYO Data Highway基本戦略」を打ち出した。同年9月、民間から12年ぶりとなる副知事に起用されて以降は、さらに精力的にプロジェクトの推進に取り組んでいる。
また、世界・アジアの金融ハブとしての「国際金融都市・東京」の実現に関する施策を担当し、世界中の金融系企業・人材の誘致、資産運用業やFintech産業の育成、グリーンファイナンスの活性化に向けた戦略の推進などに取り組んでいる。
三重県CDO 田中 淳一 (たなか じゅんいち)さんのプロフィール
18歳で起業、1999年にAIベンチャーとして法人化し、ITコンサルティング事業と広告事業の企業グループを約10年経営した。また、(株)ユーグレナ 取締役、(株)コークッキング 取締役など、社会課題解決を目指すスタートアップの経営にも携わったほか、地方創生に関連して、様々な地方自治体と連携し、ジェンダー平等・移住定住・人口減少対策などにも取り組んだ。
2021年4月より、三重県 最高デジタル責任者(CDO:Chief Digital Officer) に就任。
デジタル社会形成の方向性として「誰もが住みたい場所に住み続けられる三重県」を掲げ、ジェンダー平等を含んだ多様性や包摂に基づく「寛容な社会」を前提条件として、県民の皆さまの心豊かな暮らしと地域の持続可能性を目指し、みんなの想いを実現する「あったかいDX」を推進している。
内閣府 地域活性化伝道師、総務省 地域情報化アドバイザー、総務省 地域力創造アドバイザー、デジタル庁 シェアリングエコノミー伝道師、経済産業省 IoT/AI時代に対応した地域課題解決のための検討会議 構成員、兵庫県豊岡市 ジェンダーギャップ解消戦略会議 オブザーバーなども務める。
三重県が進めるDX政策「あったかいDX」の一環で、グループインタビューやワークショップ等、未来像の取りまとめのプロセスや同県内で取り組まれているDX事例等を収録した動画「はじまる はじめる みえのDX ~みんなでつくるデジタル社会~」を制作、公開している(下の埋め込みリンクより視聴可)。