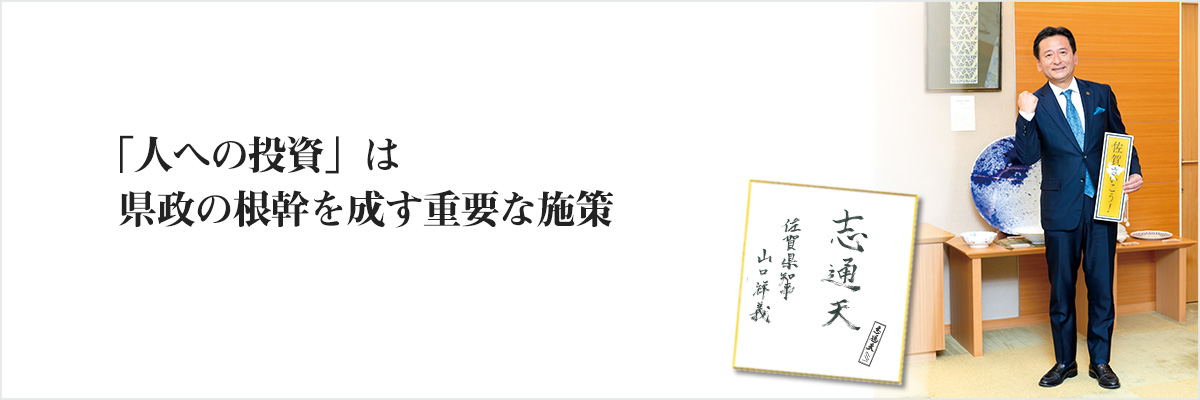※下記は自治体通信 Vol.64(2025年3月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。
4年ごとに策定されてきた県政の最上位計画である「総合計画」を見直し、大方針のみを明記した「施策方針」へと刷新したことで大きな注目を集めた佐賀県。その文量は、従来の10分の1ほどに圧縮され、数値目標も盛り込まれていない。同県知事の山口氏によると、そこには社会の激しい環境変化へ柔軟に対応すべく、現場オペレーションを重視する県政運営方針が反映されているという。これまでの成果や、今後の県政ビジョンについて同氏に聞いた。

プロジェクトやオペレーションを大切にする
―佐賀県知事として3期目も半ばを過ぎました。この間の県政をどのように振り返っていますか。
知事就任から10年になりますが、佐賀県政の特徴を考えると、「プロジェクトやオペレーションを大切にしている県政」だと思っています。たとえば、これまで4年ごとに策定してきた「総合計画」は、細かく事業立てして、数値目標も定めるという従来のスタイルを少しずつ見直してきました。そして令和5年度には、めざすべき大きな方向性のみを示す「施策方針」に転換しました。そのうえで、各年度に実施するおもな事業は、「佐賀さいこうビジョン」という薄い冊子で毎年紹介しています。
―そうした方針転換の背景には、どのような考えがあったのですか。
時代が大きく移り変わり、4年後の姿が見えてこない中では、長期計画を策定するよりも、その時々の状況を見据え、柔軟なオペレーションでビビッドに事業を打ち出すことこそ大切だと考えています。以前は、「総合計画に載っている事業をやる、載っていない事業はやらない」という議論が少なくありませんでした。
しかし、これだけ状況変化が激しい時代に、変化に合わせてビビッドに事業を打ち出さなければならない中で、「総合計画に載っているか否か」の議論に捉われていては時代に取り残されてしまいます。少なくとも、時代の先取りなどできたものではないでしょう。その象徴的な出来事が新型コロナウイルスへの対応だったと思います。あのように大規模な感染症などない前提でつくった計画を、そのまま実行できるはずがありません。やはり県政はオペレーションによって軌道修正していくことがとても大事です。大きな方針をみなで共有しておいて、実際に起きていることに対して事業を講じていく。総務省在職時から、多くの自然災害や危機管理の最前線を指揮してきた私の経験を踏まえても強くそう思います。この10年間、佐賀県庁はそういう対応ができていたと思っています。
そしてもう1つ、佐賀県政の特徴といえるのが、「質へのコミット」です。
「さがデザイン」の力を示した、「SAGAアリーナ」の成功
―詳しく教えてください。
佐賀県では、少しでも顧客満足度の高い施策・サービスを打ち出すことを大事にしており、そこにおいて知事の役割は、オーケストラの指揮者のようなものだと思っています。大きな方針を示して、個々の楽器パートの演奏はそれぞれに任せる。方針をすべてのパートに貫くことさえできていれば、楽団全体として素晴らしい音楽を奏でるように、施策の満足度も高まると信じています。その方針を貫く手法として、就任当初から採用しているのが「さがデザイン」という考え方です。
すべての部署や事業に利用者目線の「デザイン」の発想を取り入れていく仕組みで、単に表面的なデザインだけではなく、仕事の仕方とか評価の行い方とか、さまざまな部分にデザイン的手法というものを組み合わせています。そこには、佐賀にゆかりのあるデザイナーやクリエイターと築いたネットワークから、プロジェクトごとにその専門領域に精通した人材がコミットするかたちになっています。その仕組みによって、一つひとつの施策とか施設とかに命が吹き込まれると私は思っています。
―具体的な事例はありますか。
1つの例が、令和5年5月に開業したSAGAアリーナです。我々は、スポーツビジネスが広がっている世界の趨勢に触れ、それを実現するための多目的アリーナの有効性に着目していました。ちょうど国体から国スポに変わる初めての大会を佐賀で開催することが決まり、体育館の建設も議論していました。果たして、国スポのための体育館を造ることが県民の満足度につながるのか、「さがデザイン」の視点で、施設の目的から問い直す根源的な議論を重ねました。最終的には国スポの先を見据えて、世界標準のスポーツ文化を実現できる設備を備え、スポーツだけではなくライブイベント、MICEなどにも対応できる、これまで佐賀になかったエンタメアリーナの実現に向けて投資しようと決断しました。
その結果、佐賀から時代を切り拓くという強い想いを込めた、このSAGAアリーナはいま、県民の予想をはるかに超える価値を生み出しています。
未来を担う人材を輩出する「県立大学」構想が進行中
―そうした県政運営の中で、現在の最重要政策はなんでしょう。
「県立大学」の創設です。少子化の中でも、大学に進学する人の数はむしろ増えていて、佐賀県でも35年前には約2,000人だった進学者数が、いまでは約3,500人に増えています。また、県内の有効求人倍率は1.3倍*を超え、経済界からも県内産業を担う人材確保への強いニーズが寄せられています。県政の施策方針において「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」という基本理念を掲げてきたとおり、佐賀県のすべての施策の基軸には「人」があり、「人への投資」は県政の根幹を成す重要な施策だと考えています。
―どのような大学をつくろうとしているのですか。
つくると決めたからには、これからの時代に一番輝くような、新しい大学をめざしています。小・中・高校からの学びがつながり、未来を担う人材が大きく成長できる大学、地域に愛される学びの場の開学に向けて挑戦を続けます。
*令和6年12月時点

さまざまな経験を積んだ職員。満足度の高い政策を打ち出す
―満足度の高い政策を打ち出すために、大事なことはなんですか。
さまざまな経験を積んだ職員が、多様な意見を出し合うことが大事だと思います。そのために、佐賀県では積極的に中途採用を進めており、現在は職員全体に占める中途採用職員の割合は16%で、全国トップとなっています。いろいろな経験を積んだ個性あふれる職員たちが構想力、創造力を発揮し合う。その個性あふれる職員たちをまとめ、決断していくのが指揮者としての知事の役割です。
そこから生み出される政策が一人ひとりの県民に届き、約80万人の佐賀県民のみなさん一人ひとりが、少しでも幸せに前を向いて楽しく暮らしていける佐賀の姿を描いていきます。