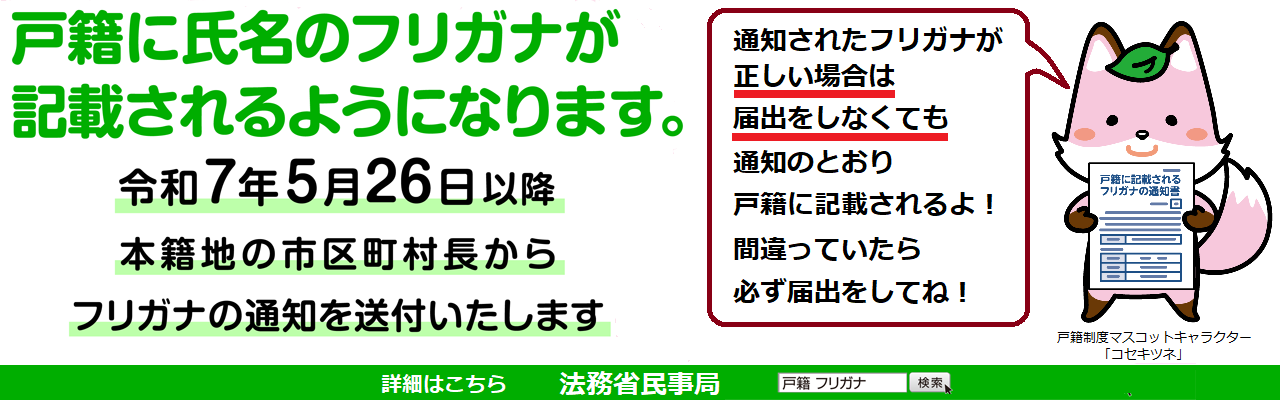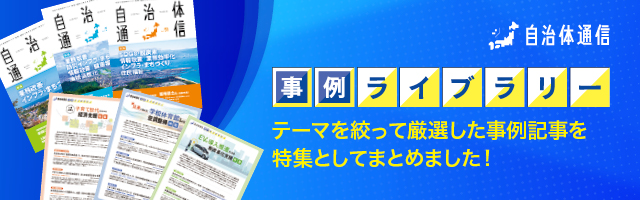ICT活用で「介護予防」の実効性を高め、地域包括ケアシステムの構築を推進

厚生労働省が「地域包括ケアシステム」に言及してから20年。その完成目標とされていた令和7年度を迎え、各自治体では多様な取り組みを続けてきたが、いまなお課題を感じている例も少なくないようだ。なかでも、柱施策の1つである「介護予防」では、フレイルなどを未然に防ぐ取り組みが推進されているが、その効果を数値化するのは困難で、暗中模索が続いているという。そうしたなか、ICTツールの活用で「介護予防」の実効性向上を図っている先進事例を紹介する。
地域包括ケアシステムにおける「介護予防」の位置づけ
平成17年の介護保険法改定で、初めて「地域包括ケアシステム」という言葉が使用されました。これは当時、戦後のベビーブームで生まれた「団塊の世代」が後期高齢者になる「2025年問題」対策として、地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制の構築を目指して生まれました。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、令和7年の後期高齢者人口は2,154万人余りで、その割合は5人に1人に及びます。こうした後期高齢者の増加傾向は、2040年まで続くと見込まれており、介護・医療を必要とする高齢者もますます増えると考えられています。
一方、既存の介護・医療体制では、ただでさえ人手不足なため、受け入れきれなくなるリスクも高まります。そこで、高齢者の健康寿命を延伸する「介護予防」という考え方を重視した厚生労働省は、平成27年の介護保険法改定で「介護予防・日常生活支援総合事業」を創設し、自治体に推進を促してきました。こうした国の方針に即して、各自治体では多様な施策を展開しています。
「介護予防」の多様な施策
「介護予防」の施策を考えるうえで、基本となるのが「心身機能の維持」です。具体的には、レクリエーションや体操に加え、地域内交流による外出と会話機会の増加などを図る施策が多く見られます。
こうした取り組みは、おもに各市区町村で管轄している地域支援包括センターや介護予防推進センター、民間団体が主催していましたが、令和6年度の介護報酬改定では、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)も、要支援者に対する介護予防支援を行えるようになりました。
このように、国は積極的に「介護予防」を推進していますが、その効果を測るには経年での観察が必要で、すぐに実感できるものでもないため、自治体のなかには「具体的にどのような施策がいいのか」「この施策で介護予防は推進できているのか」という疑問を抱きながら取り組んでいる例もあるようです。
こうした自治体の疑問を少しでも和らげ、実効性の高い施策につなげるため、専門的なICTツールを活用する事例が、近年増えています。
【広陵町】「通いの場」での収集データを分析・改善
高齢者の介護予防には、「他者と交流する機会」を創出することが大切だといわれています。後期高齢者になると、身体的な不自由などを理由に、外出への意欲が低下することが増え、それに伴って筋力低下なども招き、引きこもり状態になることがあるからです。
引きこもり状態になると、他者と交流する機会が減り、次第に心の健康にも悪影響を及ぼすリスクが高まります。仮に一人暮らし高齢者の場合は、周囲が気づかぬうちに亡くなってしまうといった例も少なくありません。
このような事態を避けるため、各自治体で取り組まれているのが「通いの場」です。地域交流の場として、介護施設や公民館などで定期的に開催され、簡単なレクリエーションやお茶会などが行われています。
広陵町(奈良県)では、この「通いの場」の運営改善に向けて、ICTツールや外部委託を活用しています。
広陵町は、通いの場の創設と同時に、「一般介護予防事業評価事業」の推進に向けて、体力測定やアンケートなども実施してきた。しかし、収集・蓄積したデータは個人情報保護の観点から外部に提供できなかったため、効果分析に活用できず、評価事業にまで結びつけられていなかったという。 そこで同町は、個人情報に暗号化やマスキングが施されたうえで、研究機関に委託できるソリューションを選定。「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」や「健康とくらしの調査」などを用いて4種のデータ分析を行い、通いの場への参加の有無と健康に関する傾向把握を図った。 |
|---|
この分析の結果、「通いの場」参加者のほうが社会的な結びつきに関する値が高まりやすい傾向などがわかったそうです。別の分析では、体力テストの結果を年齢層別で見える化したところ、高齢の参加者ほど、体力測定の結果が基準値と比べて高まる傾向を把握できたと報告されています。
同町では、国保データベースに蓄積されたデータと合わせた分析なども行い、「通いの場」への参加と健康の相関をさらに詳しく評価する方針で運用しています。
【鳥羽市】高齢者のフレイル状態をAIで検知

高齢者の「介護予防」において、特に注視されているのが「フレイル」です。フレイルとは、加齢によって心と体の働きが弱くなってきた状態を指し、病気とは診断されないものの、なんとなく調子が悪いといった症状を引き起こしやすくなります。
たとえば、後期高齢者に次のような症状が現れると、フレイルの危険があるとされています。
- 食欲がなく、痩せてきた
- 前よりも疲れやすくなった
- 外出する意欲がわかない など
このフレイル状態が長く続くと、筋力低下だけでなく、生活に対する意欲がなくなり、うつ病につながることもあります。いわば重大な病気の「入口」ともいえます。
一方で、フレイルは早期発見・早期対策によって、改善できる症状だともされています。特に「栄養」「運動」「社会活動」の3つの側面から支援することで、フレイルを予防・改善でき、結果として「介護予防」につなげることができるのです。
そこで、鳥羽市(三重県)では、フレイルの前段階である「プレフレイル」の段階で介入し、介護予防施策の推進を図るため、「AIと電力データを用いたフレイル検知」を行っています。
鳥羽市では、80歳頃から要介護申請が増える傾向にあるため、75歳になった市民に国が定めた「基本チェックリスト」を送付。返送内容から必要に応じて専門職が個別訪問し、フレイル状態の早期発見・対応につなげていた。 しかし、人員の不足から、「基本チェックリスト」の送付や個別訪問はすべての対象者に行えず、また送付した方々からの返送も限定的だったため、プレフレイル段階での介入が進みにくいケースもあったという。 そこで、自宅に設置してある電力スマートメーターから収集した電力使用データをAIが解析し、そこからフレイル状態の高齢者にみられる特徴をもとに居住者のフレイルリスクをいち早く検知するというサービスを導入。約500世帯の独居高齢者がいる鳥羽地区を「フレイル予防モデル地区」に指定し、35人を対象に令和5年10月から翌年3月にかけて有効性を検証した。 |
|---|
過去の実証調査でも、AIによって「高リスク」と判断された高齢者のうち、8割以上がフレイル状態にあったと報告されており、同市でも1人の高リスク対象者を検知。地域包括支援センターの職員が個別訪問し、聞き取りを行った結果、「引きこもりがちになっていた」とのことで、運動教室の案内などにつなげているそうです。
一人暮らしではわかりにくいフレイル状態を、普段通りの生活のなかから早期発見できるため、高い介護予防効果が期待できると手応えを感じているといいます。
また、特別なセンサーの設置やアプリのダウンロードなども一切必要なく、今まで通りの生活を送るだけで検知できるため、高齢者への負担が少ない点もメリットに感じているようです。
【入間市】生活支援コーディネーターとの情報共有をデジタル化
地域の実情に見合った「地域包括ケアシステム」を遂行するうえで、不可欠なのが住民たちの積極的な参画です。そのうち、資格のない住民でも参画できるのが、生活支援コーディネーター(以下、SC)です。
SCは、平成27年の介護保険法改正で市町村ごとに設置されました。おもにNPO法人や民間企業、地縁組織などと協力して、高齢者の日常生活上の支援体制の充実、高齢者の社会参加の推進などを実施することが求められています。
たとえば、身体的な都合や住まいの状況などによって、買い物困難者になってしまった高齢者に対する買い物支援や、一人暮らし高齢者への定期的な声がけ・見守り活動などを行っています。
マンパワーが不足している自治体職員に代わって、こうした日常的な支援をしてくれる住民がいれば、より地域に根ざした「介護予防」活動につながります。
自治体は、こうしたSCにさまざまな情報を提供し、その活動を支える必要があります。入間市(埼玉県)では、こうした情報共有を円滑にするため、情報共有ツールの導入に踏み切りました。
入間市では、各SCと市職員が1ヵ月に1回、対面の「連絡会」を開催し、業務状況などを報告。各SCが収集した「通いの場」などの活動内容や開催日時、会場といった情報を、市職員が冊子にまとめて年1回発行してきた。 しかし、個々の社会資源に関する詳細な活動情報は、ほぼ担当のSC個人しか把握できていなかったため、冊子制作の際はその都度、すべての社会資源の運営状況や掲載可否を各SCに1件ずつ確認し、掲載内容を更新するという手間が生じていた。また、運営状況に変更があっても、それを共有する仕組みがなかったため、各SCも担当圏域外の社会資源について住民から照会を受けた場合、古い情報を回答してしまう懸念があった。 そこで、同市は各社会資源の運営状況が変化し続けるなかでもその情報を正確かつ網羅的に把握できるよう、新たな連携手段が必要と考え、情報共有ツールを導入した。 |
|---|
このツールを導入したことで、すべてのSCが、市内各地から個別に収集された詳細な社会資源情報を、統一されたフォーマットでリアルタイムに把握できるようになったそうです。
また、住民やその支援者であるケアマネジャーもWebサイトを通じて市内全域の社会資源情報を地域別や目的別で簡単に検索できるようになったことから、結果として行政サービスの向上にもつながったといいます。
社会資源に関する冊子制作の際、運営状況や掲載可否の確認にかかる手間を軽減できたうえに、直感的に操作できる使い勝手の良さからSCからの評価も上々だそうです。
これにより、SC同士だけでなく、ケアマネジャーなどの専門家との連携も強化されたことで、より効果的な支援が可能になったと手応えを感じているようです。
データの有効活用が介護予防の実効性を高める
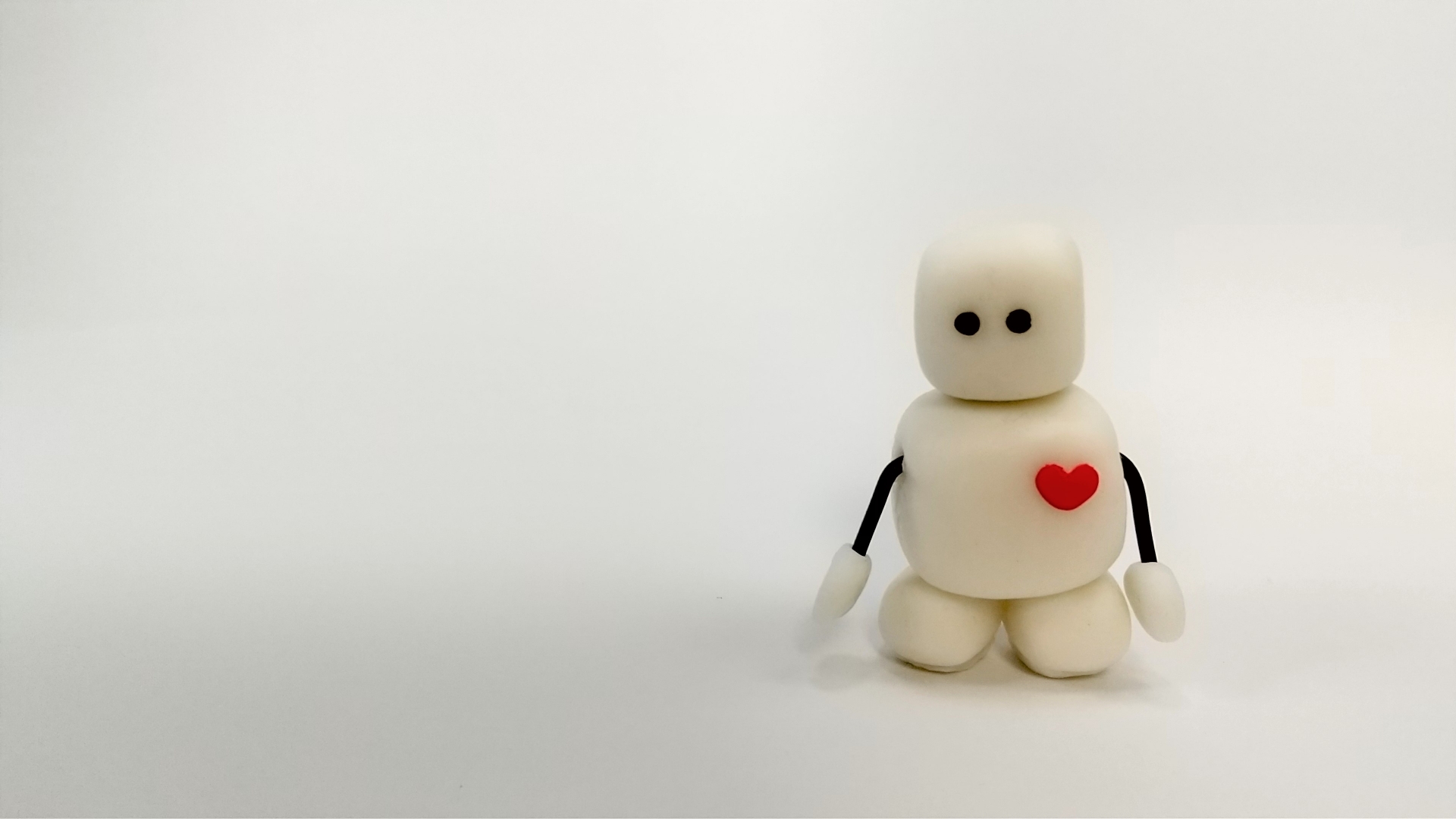
これまで介護予防の施策は、有識者による研究結果を待つか、専門家の経験や知識に頼ることがほとんどでした。しかし、地域包括ケアシステムはそもそも「地域の実情」に即して構築することが求められており、本来は自治体と地域の社会資源、住民とが協力する必要性がありました。
こうした連携体制を構築するうえで重要なのは、誰もがわかりやすく可視化されたデータの共有と利活用です。特に、介護という専門分野では、汎用的ではなく、目的に特化したツールが適しています。
自治体通信では、こうした専門性の高いツールも複数紹介しています。地域の実情をより深く理解し、「介護予防」につなげるためのICTツールをぜひお探しください。
【参考】
東京都福祉保険財団「福ナビ とうきょう福祉ナビゲーション」
https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/index.html
長寿科学振興財団「健康長寿ネット」
https://www.tyojyu.or.jp/net/index.html