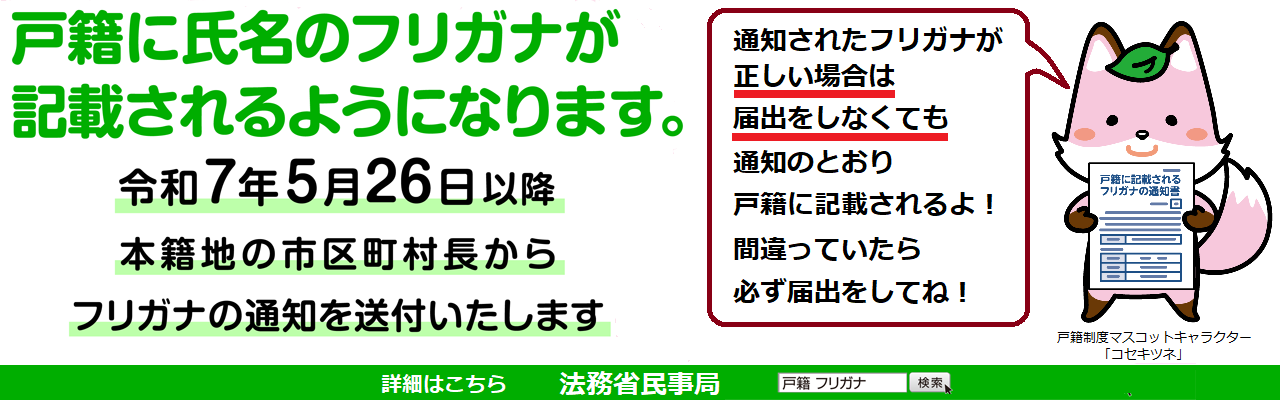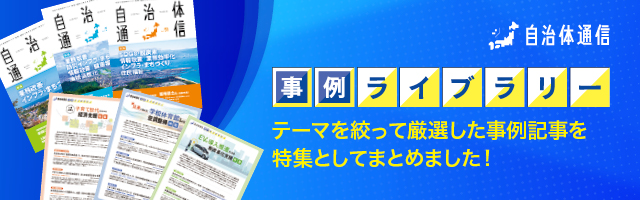脱炭素化・災害対策の強化に向けたEVの普及促進策
令和2年10月、政府は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことを宣言しました。以来、「ゼロカーボンシティ宣言」の発出をはじめ、環境先進地域を志向する動きが全国の自治体で相次いでいます。その具体的な取り組みの1つとして、電気自動車(以下、EV)の普及促進に取り組む自治体は少なくありません。また、令和元年台風15号による千葉県大規模停電や、令和6年の能登半島地震などの大規模災害時には、走る「非常用電源」としてEVが活躍し、その価値にあらためて注目する自治体も増えています。そこで本記事では、公用車へのEVの導入や、地域へのEV普及促進に向けた、自治体の取り組み事例などを紹介します。

日本のEV普及率、世界に大きく遅れ
2020年代に入り、世界のEV普及は急激に加速しています。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の新車販売台数に占める電気自動車(BEV・PHEV*)の比率は、2023年時点で18%です。2020年以降の伸び率は大きく、2020年に4.2%、2021年に9%、2022年に14%、2023年へ18%と上昇を続けています。日本のEV普及率も年々増えているものの、普及が特に進んでいる中国や欧州には大きく遅れをとっています。
ENECHANGE株式会社が一般社団法人日本自動車販売協会連合会「燃料別販売台数(乗用車)」と一般社団法人全国軽自動車協会連合会「軽四輪車通称名別新車販売確報」からまとめた、令和7年2月時点でのデータによると、EV・PHEVの新車販売比率は2.66%で、前年同月(2.81%)と比べてもやや減少しています。
一方で日本政府は、2035年までに乗用車新車販売台数における電動車の比率を100%とする目標を掲げています。公共用の急速充電器を含む充電インフラの数も2030年までに30万口まで伸ばし、ガソリン車並みの利便性実現を目指しています。こうしたなか、地域経営を担う自治体は、域内における脱炭素化の「旗振り役」としての主体的な行動が求められています。
EV普及策は「補助金」が中心
実際、地域のEV普及に向けて、自治体はどのような取り組みを行っているのでしょうか。環境エネルギー政策研究所が令和5年9月、合計239件(都道府県47件、市区町村192件)を対象に実施した調査結果は次の通りとなっています。
「Webサイトでの情報提供」25件(都道府県:20件、市区町村:5件)
「イベント開催」7件(都道府県:4件、市区町村:3件)
「公用車EV化」25件(都道府県:8件、市区町村:15件)
「EV公用車カーシェアリング」9件(都道府県:5件、市区町村:4件)
「充電器設置」8件(都道府県:4件、市区町村:4件)
「公共交通電化」7件(都道府県:1件、市区町村:6件)
「EV購入補助金」158件(都道府県:22件、市区町村:136件)
「普通・急速充電設備設置補助金」40件(都道府県:12件、市区町村28件)
「V2H設置購入補助金」62件(都道府県:6件、市区町村:56件)
「EVバス・タクシー導入補助金」6件(都道府県:5件、市区町村:1件)
調査結果からは、EVやV2H、普通・急速充電設備の購入に対する補助金の交付が、自治体によるEV普及政策の中心となっていることが見て取れます。また、普段使用する公用車のEV化に取り組む自治体も多いほか、民間事業者とのパートナーシップのもと、土日祝日などに公用車EVを一般向けにシェアリングするといった取り組みを進める事例も生まれています。
以下からは、EV普及促進に向けた自治体のユニークな取り組み事例を紹介します。

【長野県】予約管理×充電制御でEV運用を最適化
長野県では、令和3年6月に「長野県ゼロカーボン戦略」と合わせ、県の事務事業における地球温暖化対策の取り組みをまとめた「第6次長野県職員率先実行計画」を策定。このなかで、重要施策の1つに「公用車のEV化」を掲げている。同県は令和2年度からEVを試験的に導入してきたが、この計画に沿って更新時期を迎えたガソリン車を順次EVへ切り替え、令和5年度には全庁で計88台にまで増やしてきた。ただ、その段階でおもに2つの問題が顕在化してきたという。 1つは、「電気料金の増大」だ。公用車の利用はほとんどが日中のため、EVの充電タイミングが夕方に集中することで、ピーク時の電力需要が従来よりも大幅に伸び、契約電力を超過するおそれが出てきた。もう1つは、「公用車の予約・配車管理の複雑化」だ。同県では、軽自動車と普通車の2車種のEVを導入し、ガソリン車と合わせて運用しているが、航続距離はそれぞれに異なる。そのため、行き先や用途などを考慮し、予約状況に応じて最適な配車を行う必要がある。EVの台数が増えてくることでそれらの調整が複雑化し、従来のように人手で管理することが難しくなってくることが予想されていた。 そこで、DX戦略推進パートナー連携協定を結んだ民間企業から提案を受けたのが車両管理システムだった。これは、利用者が日時・目的地・希望車種などを入力して予約すると、システムが庁内の公用車利用全体のバランスを鑑みて車両を配車してくれるサービスだ。EVで行ける距離にはEVを優先的に配車し、行けない距離には燃費の良いガソリン車が配車される。それにより、EVの稼働率を最大限に高めながら、公用車全体を無駄なく効率的に運用できる仕組みという。あわせて別の部署では、別の民間企業が提供する充電制御システムの導入も検討していた。これは、複数EVの間で充電タイミングを調整・制御することにより電気料金の上昇を抑制するものだ。 同県では、この2つのシステムを連携させることで最適な形で運用改善を図れるのではないかと考え、実証実験を実施した。実験は、先行的にEV導入を進めている松本合同庁舎で令和5年7月11日から8月末まで実施。EV21台、ガソリン車48台の計69台を対象とし、EVを配備または配備予定の15部署、469人が参加した。 |
|---|
長野県はこの実証実験を経て、充電制御による消費電力のピークカットの効果が確認できました。環境部の試算では、1台当たり年間2万4,348円、6kWの急速充電設備を採用する場合は、じつに5万8,440円の電気料金の削減効果が見込まれたそうです。一方、車両管理システムによる効果としては、年間9万168円の削減が見込まれるとの試算が出ました。この数字は、一括管理と配車制御によってもっとも電費効率に優れる軽EVを最大限活用するなど、最適な形でEVを配備することで得られる初期費用削減や電費改善、電力ピークカットによる電気料金削減といった効果を加味したものだそうです。
同県によると、今回の実証実験は、従来の部署ごとによる車両管理を踏襲して予約・配車を行ったもので、上記の数字はあくまでも試算によるものです。車両管理の効率化効果を最大化するためには、部署の垣根を越えた全庁による一括管理が望ましく、従来の個別最適から目指すべき全体最適へといかに移行するかが今後の課題としているそうです。
【栃木県】試乗会でEVへの「先入観」払拭へ
栃木県は、乗用車の1人当たり保有台数が全国2位の車社会であり、県全体のCO2排出量のうち、交通分野が約3割と高い比率を占めている。そのため、令和4年3月に策定した「2050年とちぎカーボンニュートラル実現に向けたロードマップ」では、交通分野の目標として、2030年度までに乗用車保有台数の6割をEVなどの電動車に置き換えることを掲げた。そのうえで、商業施設でのEVの展示や、EV購入補助金の創設など、普及促進策に取り組んできた。そうしたなか、住民を対象にアンケートを実施したところ、EVに対する人々のイメージを改善することも必要だと考えた。 そのアンケートでは、EVの購入について「検討したことがない」「検討したが購入しなかった」と答えた人が全体の96.5%を占めていた。その理由には、経済的なもの以外では、「充電できる場所が少ないイメージがある」「航続距離に不安があった」といった、イメージに関するものが特に目立ったのだ。これらネガティブなイメージはいずれも、EVに乗ったことがないために抱く、漠然とした先入観によるものと、同県は仮定。今後、EVの普及を促していくには、そうした先入観を払拭し、EVに対する理解を深めてもらうことが必須だと考え、民間企業の協力を得て、EVの試乗会を実施した。 |
|---|
栃木県によると、このEV試乗会の特徴は、複数メーカーのEVを乗り比べできるという点でした。価格や特性が異なる複数の車種に実際に触れてもらうことで、EVをより身近に感じてもらい、EVに対して抱いていた先入観を払拭し、理解をより深めてもらえると期待したそうです。会場には、国内メーカー4社の6車種に加え、乗り比べ用のガソリン車1車種を用意。県内の9市町と民間事業者25社から合計59人が参加しました。
実際にEVを試乗してみた参加者の感想としては、「ガソリン車と比べて加速性や静粛性が優れている」など、これまでイメージとして持っていなかったEVのメリットを体感できたという声が多くあったそうです。アクセルペダルを少し踏み込むだけでグンと加速する快適さは、車好きの人にとっては大きな魅力になるでしょう。
もう一つの成果としては、参画事業者による講座や展示を通じ、EVの運用に対する参加者の不安の払拭を図れたことです。航続距離に不安があったという参加者からは、「軽タイプのEVでも150kmは走行できることを聞き、十分に利用できると思った」といった感想が寄せられましたとのことです。講座に関しては、今後の要望として「ガソリン車とのコスト比較を行ってほしい」「EV導入の失敗事例も知りたい」といった声もあがり、参加者の間で「EVをより深く理解したい」という関心が高まったのを、同県の担当者は感じているようです。今回参加できなかった自治体や事業者からも、他地域や次年度の開催を求める声が多くあるため、今後も同様の試乗会を開催していく方針とのことです。
【岸和田市】「リユース車活用」の可能性を追求
岸和田市(大阪府)は令和3年に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、地球温暖化対策実行計画「事務事業編」の策定に着手した。そのタイミングで、民間企業から、EVに関するある実証実験の提案を受けた。その内容は、業務でリユースEVを一定期間使用し、バッテリー診断などによる検証を経て、その活用可能性を探っていくというものだった。この実証実験では、EV普及のハードルとなっている「費用」や「性能に対する不安」といった課題の解決策を検証するものだ。この検証に公用車を走らせて取り組むことは、EV利用への市民のためらいや不安を払拭するのに有効だと期待した。また、同市を舞台にこの実証実験を行うことにも意味がある。EVは、どのような道路をいかに走行するかでバッテリーの劣化度合いが異なるとされる。そのため、海も山も住宅地もある岸和田市でEVの活用可能性を探ることは、広く泉州地域におけるEVの活用モデルづくりにつながると考えたそうだ。実証実験は、令和6年2月に3台のリユースEVをリース方式で導入し、実施している。 |
|---|
実証実験は、大きく3つの観点に分けた検証を通じ、それぞれの成果を目指しているそうです。1つ目は、「リユースEVの耐用性」に関すること。ここではたとえば、「バッテリーの充電能力を低下させない運行ノウハウの蓄積」などを成果として目指しています。低価格のリユース車でも十分に活用できることを証明できれば、広くEVのリユースの促進にも寄与できるものと、同市は期待しています。2つ目は、「公務に馴染むEV運用の見極め」です。具体的には、公用車としての運用に適した車種や用途、運行・管理方法を特定し、庁内でのリユースEVの導入拡大を目指します。
3つ目は、「バッテリーの再利用」の可能性を探る検証です。バッテリーは、劣化によってEVを駆動させるのに十分な最大容量を確保できなくなっても、インフラとして活用できる可能性が大きいからです。たとえば、近年開発が進むEV用交換式バッテリーは、街路灯や非常用電源などに転用できます。同市は、この交換式バッテリーに大きな将来性を感じており、「バッテリーを専用ステーションで交換し、その容量の差分を対価として支払う」といったインフラ構想を考えています。今回の実証実験では、そうした構想の実現可能性も探っていくものとしています。
同市は、市民とともに脱炭素に取り組んでいくために、多くの人々に身近な自動車は重要な存在だと捉えています。EVにはまだ、「高額」や「実用面での不安」といったイメージがありますが、この実証実験でそのイメージを払拭し、EVを手頃な価格でも購入できる、身近で便利な車にしていきたい考えのようです。今後も、EVやモビリティに関する幅広いソリューションを持つ民間企業と協力しながら、EVの導入や活用を促していく方針です。
官民連携から生まれる成功事例
ゼロカーボン社会の実現に向けた施策や、災害対策として、いま多くの自治体がEVに関心を寄せ、公用車へのEV導入や、地域の事業者・住民へのEV普及促進に取り組んでいます。その現場では、導入コストのほか、航続距離や充電をめぐる実運用面での不安、住民の環境意識の醸成などが、課題となるケースも少なくありません。しかし、そうした課題に向き合う自治体の現場においても、民間企業のノウハウや経験を積極的に取り入れることで、上記で紹介した以外にも、数々の成功事例が生まれています。
たとえば、EVの導入コストを捻出する取り組みとしては、小松市(石川県)や日向市(京都府)などにおいて、ガソリン車を含む公用車の保有台数を適正化し、削減した費用をEVの購入資金に充てるといった事例が生まれています。住民の環境意識の醸成をめぐっては、入間市(埼玉県)が、公用車のEVを平日夜間と休日に一般に貸し出すシェアリングを行うほか、庁舎の駐車場屋上などに設置された太陽光発電設備で発電した電力をEVに供給する仕組みも構築するといった取り組みが進んでいます。
こうした、全国で生まれている官民連携の成功事例は、EVのさらなる普及促進につなげるための、良い参考になるでしょう。
【参考】
IEA「Global EV Data Explorer」
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer
環境エネルギー政策研究所「自治体EV普及政策調査報告書 2023(研究報告)」
https://www.isep.or.jp/archives/library/14508