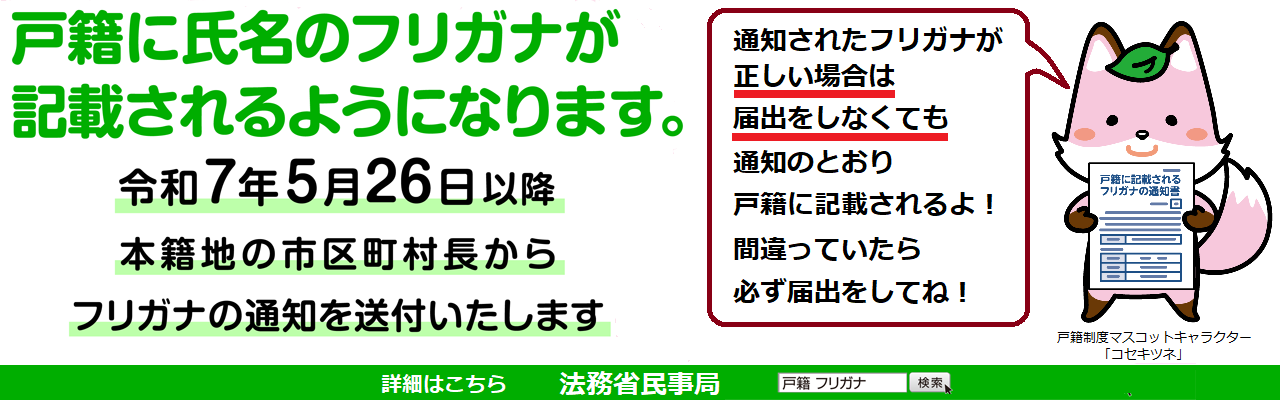自治体における郵便物発送業務の課題と解決策

全国の自治体では日々、部署を問わずに多くの通知や帳票などを住民に向けて発送しています。その現場では、発送物を郵便局に差し出すための集計作業や、文書を封入・封かんする作業に、職員が負担を感じているケースも少なくありません。本記事では、郵便物発送業務をめぐる課題や、その課題の解決に向けた自治体の取り組み事例などを紹介します。
「差出票」の作成が総務部門の負担に
ほとんどの自治体では、発送する郵便物の量が多いため、一般的には「料金後納」という郵便の仕組みで発送物を郵送しています。料金後納とは、毎月50通(個)以上の発送物を差し出す事業所を対象とし、取扱郵便局の承認を受ければ、切手を貼らずに発送できる仕組みです。郵便料金は、1ヵ月ぶんをまとめて翌月に一括、支払います。この料金後納を活用する場合は、郵便物の種類や重量・サイズ、通数、1通あたりの料金、合計金額などを記載した「差出票」を、郵便局員に提出する必要がありますが、この作業に職員が負担を感じているケースが少なくありません。集荷や郵便局に差し出すまでの時間に間に合うよう、通常業務の合間に種々雑多な大量の発送物の重量を計測し、通数を数える作業に心理的な負担を抱えているのです。
また近年は、郵便局が発送物の集荷サービスを終了したことで、自治体職員の負担増につながっているケースもあります。日本郵便は平成30年6月末、労働力不足などを背景に、法人向けの集荷サービスを終了しました。発送量の規模が大きな自治体向けには、それまで通り集荷を続けているケースもありますが、サービスが終了となった場合は、職員が郵便局まで直接差し出しに出向くか、発送物に1通ずつ切手を貼って最寄りのポストに投函するといった選択が迫られることになります。いずれも、郵便物発送に伴う職員の負担はさらに増大してしまうでしょう。
スピードと正確さが求められる封入・封かん作業
自治体における郵便物の発送に伴う作業は、発送前の集計作業だけに限りません。税務や福祉、ふるさと納税といった部門では、定期的・断続的に発生する、「封入・封かん」作業に労力がかかっているケースもあります。作業そのものは、文書や帳票を紙折し、封筒に入れてのりづけするという単純なものですが、大量の通数を取り扱うため、繁忙期には部署の職員が総動員され、数日間、この作業につきっきりになってしまうことを課題と感じている自治体が多いようです。また、単純作業が長引くなかでは、誤封入を起こしてしまうリスクも高まります。
「自動化」という選択肢
ここまでに紹介したような郵便物の発送業務をめぐる課題について、有効な解決策となりえるのは、発送物の集計作業や封入・封緘作業を機械で自動化することです。たとえば、発送物の集計については、「郵便料金計器」という機械を活用することで、大きな業務効率化の効果を期待できるようになるでしょう。郵便料金計器とは、郵便局の承認を得た消印と郵便料金を発送物に印字する機械です。この機械に通して印字された発送物は、差出票を提出する必要がありません。そのため、1通ずつ手作業で料金を算出する必要もなく、切手を貼らずにそのまま郵便物として送ることができるので、おもに総務部門の職員の負担軽減につながります。
以下からは、こうした発送業務の自動化を進め、職員の業務効率化につなげた自治体の事例を4件、紹介していきます。

【秋田県美郷町】発送物の集計は職員1人の「短時間作業」に
美郷町では、各原課の職員が発送物を総務課にもち込み、それを総務課の職員が差出票とともに郵便局員に手渡す形で発送業務を行っていた。各課の担当者は総務課にもち込む前に、発送物の重量を1通ごとに量り、料金別の発送物の数を記載した集計票を作成。その集計票の内容と実際の郵便物を、総務課の会計年度任用職員が突合したうえで、1枚の差出票にまとめていた。単純作業ではあるものの、令和2年以降はコロナ禍を背景に新たな業務が全庁的に増えたため、職員がこれらの集計作業に感じる負担は大きくなっていた。 総務課におけるこの集計作業には、普段でも約2時間、郵便物が多いときは、半日かかることもあった。各原課においても普段、30分程度の時間がかかっていたそうだ。そのため、全庁的に生じるこの煩雑な作業の負担をいかに解消するかを、課題と感じていた。そうした折に、一連の集計作業を自動化する「郵便料金計器」の存在を知り、導入を検討。日々の集計作業にかかる人件費と機械の賃借料を比べてみると、明確な費用対効果が見込めたため、導入に向けた予算化はスムーズに進んだそうだ。検討開始から1年後の令和3年6月には郵便料金計器を導入できた。 |
|---|
郵便料金計器の導入後、美郷町の各課の職員は、発送物の通数を数えたり、重量を量ったりする作業がほとんどなくなったそうです。郵便料金計器に通した郵便物には、郵便局に承認を得た印影と郵便料金が印字され、そのまま郵便局員に手渡せるためです。これにより各課の担当者は、基本的には郵便物をそのまま総務課にもち込むだけで済むようになりました。
この運用により、発送物の集計作業はすべて総務課に一元化される形となりましたが、総務課の職員にかかる負担も大きく軽減されたそうです。郵便料金計器に通した郵便物は差出票の添付が不要になるうえ、同町が導入した機種は、1分間で最高180通のスピードで集計できるため、総務課での作業時間は30分程度に短縮されたのです。
このほか、手作業と異なり、集計のミスを心配する必要がないため、職員の精神的な負担も軽減されました。集計作業の業務負担が減ったことで、会計年度任用職員は別の業務に専念する余裕や時間的なゆとりを得られるようになったそうです。
【北海道白老町】職員負担を増やさず適正収納の厳格化に対応
自治体にとっては、郵便物に割引料金を適用させることも、財政上の負担を抑えるために重要な取り組みですが、近年は郵便局において「適正収納の厳格化」が進み、自治体職員が割引料金を適用するための集計作業は、より慎重さが求められるようになっています。ここでは、郵便料金計器の活用を通じ、割引料金を適用するための集計作業で成果を得た、白老町の事例を紹介します。
白老町では、「町内宛で、かつ形状が同じ」発送物に関しては原則、火曜日または木曜日を発送日とし、100通以上集まった段階で総務課がまとめて郵便局員に手渡している。こうした方法を取るのは、「※郵便区内特別郵便物」を可能な限り適用させ、郵便物の発送コストを全庁で抑えるためだ。 以前はこの集計作業を人手で行っていたが、郵便局による適正収納の厳格化が進むなか、「割引料金の適用条件に合う発送物だけをいかに正確に集めるか」という課題を感じていた。封筒の形状や封入物が同じ発送物の場合、たとえ重量が規定をわずかに上回るものが混じっていたとしても、見たり触わったりするだけでは気づきにくい。そうした郵便物は割引料金が適用されないため、郵便局から差し戻され、その度に現金や小切手で正規料金を支払うというムダが、しばしば発生していたという。重量が規定を上回る郵便物は、計量することで事前に見つけ出すことはできるが、封筒の形状と封入物が同じ郵便物を100通以上の束から1通ずつ計量していくのも非効率的であり、課題と感じていたのだ。 |
|---|
白老町では、そうした課題を感じたのをきっかけに、郵便料金計器を令和4年7月に導入しました。差出票の作成が不要になるといった郵便料金計器本来のメリットだけでなく、そのメーカーの機械は、郵便区内特別郵便物の集計に役立つ「重量制限」機能も実装されていることも評価ポイントになったそうです。
それは、発送物の重量が事前に設定した数値を超えた場合には印影と料金を印字せず、機械の稼働を自動停止させる機能です。この機能を活用すれば、割引料金を適用させたい発送物を機械に通すだけで、規定の重量以内の発送物だけに「郵便区内特別」の印影と料金を印字できるのです。割引料金を適用しない通常の郵便物の集計や、各課に予算を振り分けるための毎月の集計作業も省力化できており、「郵便料金計器1台の導入で得た成果は非常に大きい」と職員は感じているそうです。
※郵便区内特別郵便物:郵便物の宛先や数、重量などの一定条件を満たした場合に料金が割り引かれる制度
【兵庫県川西市】1時間で最高3,500通を正確に封入
ここからは、発送物の「封入・封かん」作業を自動化して、成果を得ている自治体の事例を紹介します。
川西市の市民税課では、年間を通じてさまざまな通知や帳票を住民に発送している。なかでも「市民税・県民税申告書(以下、申告書)の発送」は、特に職員が直接携わる部分が大きな業務だ。同課が発送する郵便物のなかでも発送数が1万通を超えるようなものは、文書の封入・封かんを含めて業務全体を外部に委託するケースが多い。これに対し、「申告書」は発送数が約3,000通にとどまるため、発送にかかわる業務はすべて市民税課の職員が直接行ってきたのだ。3,000通もある文書の封入・封かんを完全な手作業で行うことは、職員にとって業務負担の大きいものだった。作業は3人の職員で分担していたが、それでもほぼ丸3日間かかっていた。その間、職員は通常業務を行えなくなるうえ、作業場所として会議室を3日間、専有することになり、他部署の会議室利用にも支障を来してしまっていた。また、住民に文書を発送する期限も決まっているなか、スピード感をもちつつ誤封入を起こさないよう慎重な作業が求められるため、職員にかかる精神的負担も大きかった。 そうした負担を感じていたのは、市民税課の職員だけではなかったようだ。総務課が実施した調査では、同市には福祉部門などさまざまな部署で年間約5,000時間もの封入・封かん作業が発生していたことがわかった。そこで同市では、複数の部署においてこの作業の効率化を図るために、令和2年から「封入・封かん機」という機械の導入に向けた検討を始めた。 この機械は、文書と封筒をセットしてボタンを押すと、自動で封入とのりづけを行えるものだ。同市では令和2年、業務効率を高めるための「職員提案」が募集され、そこである部署からこの機械の導入が提案されたのだった。機種選定の際は、導入後すぐに多くの業務で活用できる仕様を重視したそうで、封入・封かん機の導入を決め、令和3年6月から運用を始めた。 |
|---|
川西市が導入した封入・封かん機は、1時間当たり最高3,500通のスピードで処理を行えるため、同市市民税課において従来3日間かかっていた「申告書」の封入・封かんは、数時間で完了できるようになったそうです。また、文書は機械によって正確に封入されるため、職員は誤封入を起こさないよう手元の文書に何時間も意識を集中させるような精神的負担も感じなくなったとのことです。
こうした成果は多くの部署や業務に広がっており、総務課によると、封入・封かん機を使って処理した文書の数は、導入当初の令和3年度は1ヵ月平均9,000通でしたが、令和4年度には1ヵ月平均2万4,000通に増えたそうです。
【兵庫県西宮市】封入作業の自動化が生んだ「3週間」のゆとり
発送物の封入・封かんは、外部に作業を委託することで職員の負担軽減を図る自治体も多くありますが、その場合、事業者から納品されるまでに時間がかかってしまうという別の課題に直面してしまうケースも少なくないようです。ここでは、従来外部に委託していた封入・封かん作業を、機械で内製化することで、業務時間に大きなゆとりを生んだという、西宮市の取り組みを紹介します。
西宮市の保育入所課では、年間を通じて、保育所への入所や保育料などに関する通知物を発送している。この業務は、印刷した通知物を封入・封かんする作業が中心となる。原則的にはすべて職員が自ら行っているが、年2回発送する「保育料の決定通知」については、1回の発送量が約1万2,000通と膨大なため、職員の負担軽減を目的に、作業を外部に委託していた。しかし、それにより委託期間中の変更分の差し替えなど、大きな手戻りが毎回生じてしまっていることを課題と捉えていた。 委託先事業者が封入・封かん作業を完了させるまでのリードタイムは約3週間確保していたため、その間、宛先の住民の引っ越しや婚姻などの事情により、一部の発送物に宛名などの変更が生じる。職員はこの変更に対応するため、事業者による作業の完了後、文書を差し替え、封かんし直すという作業も行っていたのだ。その作業が必要な発送物は毎回300通ほどあり、その度に職員が3~4人がかりで半日をかけて封入・封かん作業を行っていた。 そうした課題を感じていたさなか、同市は近隣自治体と情報交換するなかで封入・封かん機の存在を知った。この機械を使って作業を内製化すれば、迅速かつ柔軟な発送業務を実現できそうだと期待し、機械の導入を決定。令和5年6月から運用を始めた。 |
|---|
川西市では自動化機械の導入後、封入・封かん作業そのものに限らず、発送業務全体に大きなゆとりが生まれました。従来、3週間を確保して外部に委託していた封入・封かん作業は、わずか2営業日で完了できるようになったのです。これによって捻出した約3週間は、コア業務ともいえる「保育料の算定」にたっぷりと充てられるようになったそうです。封入・封かん作業は発送直前にまとめて行っても間に合うようになったため、「変更のあった文書を封かん後に差し替える」というムダも減らせているとのことです。いまでは、ほかの通知書の発送業務にも封入・封かん機の活用を始めており、それまで数時間かかっていた作業時間を十数分程度に短縮できたといった効果が表れているようです。
機械でできることは機械に
DX推進の機運が高まり続ける昨今、多くの自治体では、デジタルの活用によるオンライン化・ペーパーレス化を目指す取り組みが進んでいます。しかし、それでも紙の文書や帳票を発送する業務は、まだまだなくならなさそうです。むしろ、住民サービスの多様化・複雑化に加え、職員の人手不足といった背景から、「発送物の集計や封入・封かんといった作業に職員が抱く負担感は、従前よりも増した」と感じる自治体も少なくないようです。発送業務は今後もしばらく残ると考えられる以上、限られた人手で重要な文書・帳票をスピーディかつ正確に発送するには、機械による作業の自動化こそが、業務効率化に向けたもっとも現実的で、有効な解決策と言えるでしょう。本記事で紹介したような機械を導入し、大きな成果を得ている自治体は、いままさに急速に増えています。自治体通信では、そうした事例を数多く紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
【参考】
日本郵便株式会社「料金計器別納」
https://www.post.japanpost.jp/send/fee/how_to_pay/keiki_sepa_pay/index.html