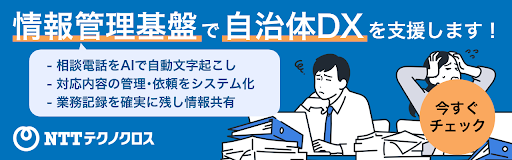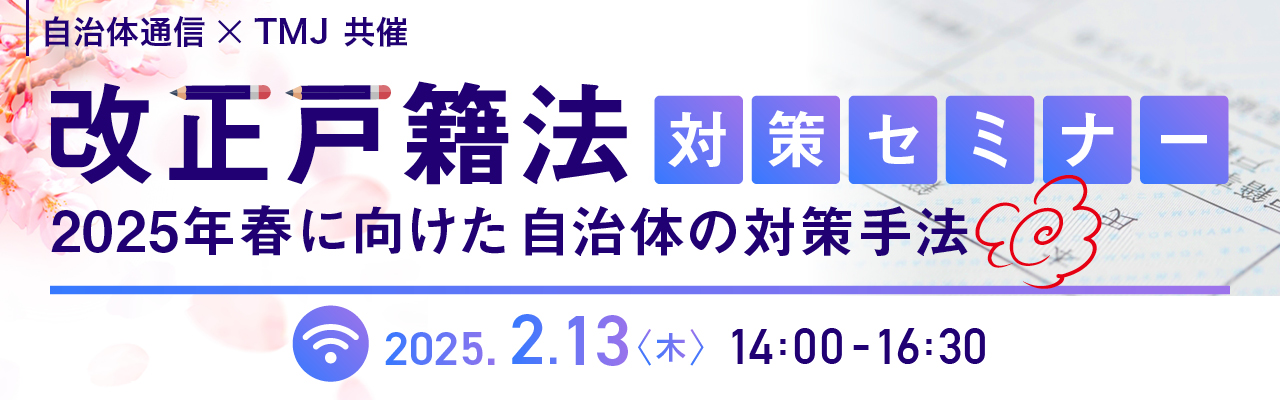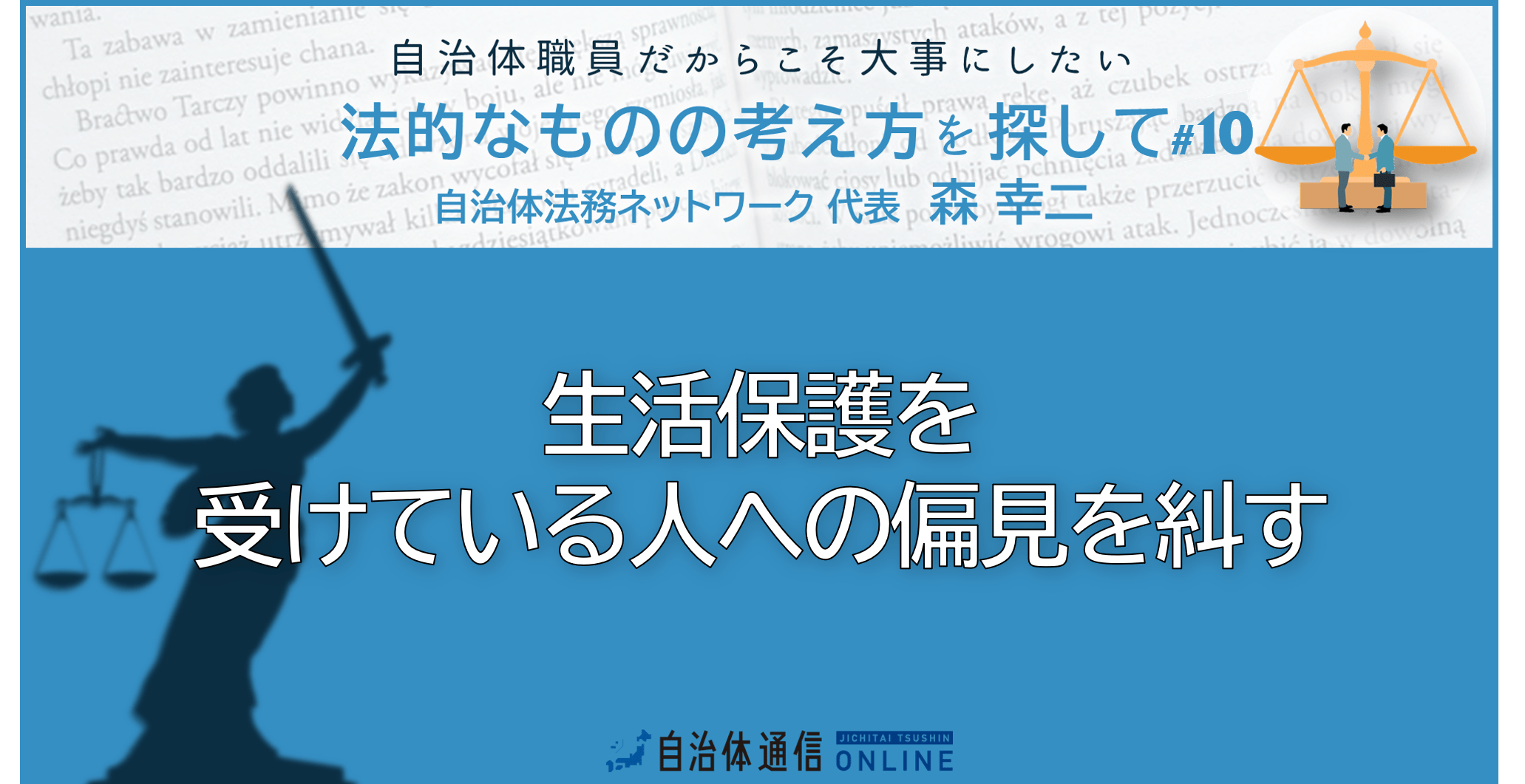

自治体向け法務研修等を500回以上行った実績がある自治体法務ネットワーク代表の森 幸二さん(北九州市職員)が「法的なものの考え方」をお伝えする本連載。今回は生活保護について。補助金や公立学校の公費負担教育費などと比較しながら生活保護の本質を明らかにし、自治体職員がもつべき考え方をお伝えします。生活保護を受けている人は「パチンコをする権利」はないのか?
生活保護を受けている人たちへの偏見
普段の付き合いの中で、「このひとは信用できる人だ」、「この人は優しい、人に思いやりのある人だ。」、「この人(だけは)常識をわきまえている。」と感じる人がたくさんいます。
その意味では(意味でも)、私は、比較的(とても)、人間関係に(人に)恵まれているほうだと(だから、この関係性の中に居続けることができるのだと)思います。
しかし、そんな私でも、ある事柄については、彼らから一瞬で興ざめする言葉を聞いてしまうことが年に何回か(平均すると年3回くらい)あります。
それは、「あの人は生活保護を受けている。恥ずかしいことだ」とか、「あの人は生活保護を受けているから、働かずに税金で食べて(食べさせてもらって)いるのだ」という趣旨の言葉です。
「彼ら」の中には自治体職員も含まれています。
では、生活保護を受けていることが本当に恥ずかしいことなのか、また、生活保護を受給することが他の権利と違う特別な恩恵なのか、私が、そのどちらについても「そうではない」ことをここで証明してみたいと思います。
直接保障制度と補助制度への評価
私が、農林部門の職場で働いていたころ、山間部など農業を営む条件に恵まれていない地域で一定期間、一定条件で営農する場合には所得を保障しましょう、という制度が始まりました。この制度のおおまかなくくりは、所得自体を保障するのですから、生活保護と同趣旨です。
若かった私は、「所得を保障するなんて、何て不公正な制度だ。農家を甘やかしているだけだ。今までどおり、補助金で農家を支援するべきではないか」と考えました。
でも、県のある職員(ここではAさんと呼びます)からこの制度の目的や設計の説明を受けて、「なるほど。そうだ!」と自分の考えを修正できました。
Aさんの説明を思い起こしてみます。
①職業についている人や企業を支援する方法としては、「補助金(を出すこと)」と「所得(を)保障すること」とがある
➁現在は、「補助金」が主流である
③しかし、補助金は不公正な一面を持っている
④なぜなら、「市場(社会における競争あるいは競争の場・機会)を乱す」からだ。
⑤例えば、農家の森さんが、キャベツを生産するのに、利益も含めて1個(玉)あたり90円かかったとする
⑥一方、市場には、同じ品質のキャベツが80円で出回っていたとする
⑦そうすると、森さんのキャベツは売れない。市場で敗北する
⑧でも、キャベツの生産について、1玉あたり30円の補助金(いわゆる3分の1補助)を支給する制度ができたとする
⑨森さんは当然に補助金を申請する
⑩森さんは、60円でキャベツを出荷することができる。そして、実際に市場に出す
⑪森さんのキャベツが売れて、ほかの誰かのキャベツが売れなくなる
結果:本来、敗者であるはずの森さんが補助金によって市場の勝者になってしまう。反対に勝者であるべき誰かが敗者となる。これでは、市場の公平性が失われる。社会に迷惑をかける。これが、国際規模の市場であればなおさらだ
結論:補助金は市場を乱す
であるのならば、補助金など出さずに、補助金行政を所得保障政策にシフトさせて、「市場で、堂々とガチンコで勝負してください。その結果、負けたら(十分な収入が得られなくなったら、生活できなくなったら)、所得を保障します」のほうが、公正なのだという理由です。
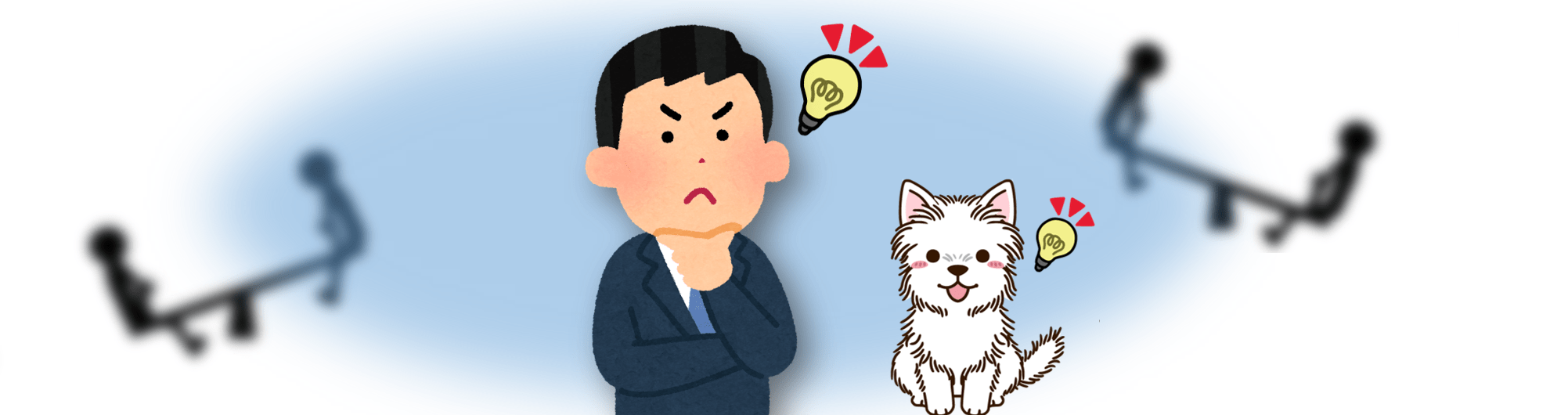
補助金を受けている人の意識
あるトマト農家に、視察に行ったことがあります(ちなみに、農業にくわしい当時の同僚が語っていたところによれば、生物学的にはトマトは野菜ではなく果物なのだそうです)。
その農家の畑では、ガラスハウス(見た目はビニールハウスに似ているものの、ビニールハウスよりもずっと立派で、ビニールハウスとは全く異質のもの)で、水耕栽培(土に植えずに空中にトマトが実っている)をしていました。
その農家さんは、誇らしげに「これからの農家は、企業と同じような経営感覚がなければダメです。私は、毎年●●●万円の収入を得ています。専業農家として経済的に自立しています」と語っていました。
視察メンバーのある職員Mが質問しました。「そのガラスハウスの設置費用について補助金を受けていますか?」農家さんが、当然のことのように(張っている胸をそのままの状態にして)答えました。「補助金は出ています。費用の3分の2です。」
補助と所得補償の逆転
日本には、世界に冠たる大企業がいくつもあります。その従業員さんたちはおおむね高水準の給与を得ているようです。一方で、失業などの事情で生活保護を受給したり、そうでなくても大企業の従業員ほどには多くの収入を得ることができずに、厳しい経済状況に置かれている人たちもたくさんいます。
その大企業のいくつかは(ひょっとするとその多くは)、国や自治体から多額の補助金を受けています。それだけではなく、私たちが、その企業の製品を購入する際には、減税措置がなされていることも少なくありません。
仮にその大企業の従業員の人たちが「あの人は生活保護を受けている。恥ずかしいことだ」とか、「あの人は生活保護を受けているから、働かずに税金で食べて(食べさせてもらって)いるのだ」と発言している、あるいは、考えているとしたら、それは、まさに「市場の不公正」の具現化といえるのではないでしょうか。
人権についての理解
生活保護を受けている住民がパチンコなどのギャンブルをしているのを見かけたときには、自治体に知らせることを促す条例が、ある自治体で制定されました。
下の会話は、その条例について、当時、私とある同僚とが交わした内容です。
同僚「生活保護を受けているのだからギャンブルをしてはいけないよね。当然だね!」
森「そうかな? ギャンブルにのめり込むことはよくないけど、生活保護を受けている人がギャンブルする権利がないとは思わないな」
同僚「森さんは、生活保護の実態を知らないからそんな甘い考えを持つんだよ。ぼくは、ケースワーカーの経験があるからね。彼らは、公費で、つまり、住民の税金で生活しているんだよ。ギャンブルなんかもっての外だよ」
森「同僚さんには、確か子どもさんが2人いたよね」
同僚「2人とも小学生だよ」
森「あなたは、ギャンブルはする?」
同僚「パチンコはしないけど、競馬は大好きだよ」
森「じゃあ、あなたも競馬を止めるべきだね」
同僚「どうしてだい?」
森「あなたの子どもの教育にも生活保護の費用と同じように、もっと、はっきりといえば、ひとり暮らしの人の保護費よりも、ずっと大きな額の公費、つまり、あなたが言うところの税金がかかっているからだよ。仮に義務教育の費用が無償でなくなったとしたら、あなたは、競馬ができなくなると思うけど」
同僚「ぼくは自分で働いて得た給与で競馬をしているんだから、生活保護を受けている人がパチンコをしているのとは全然違うよ! …でも、森さんの考え方も一理あるかもしれないね。よく考えてみるよ」
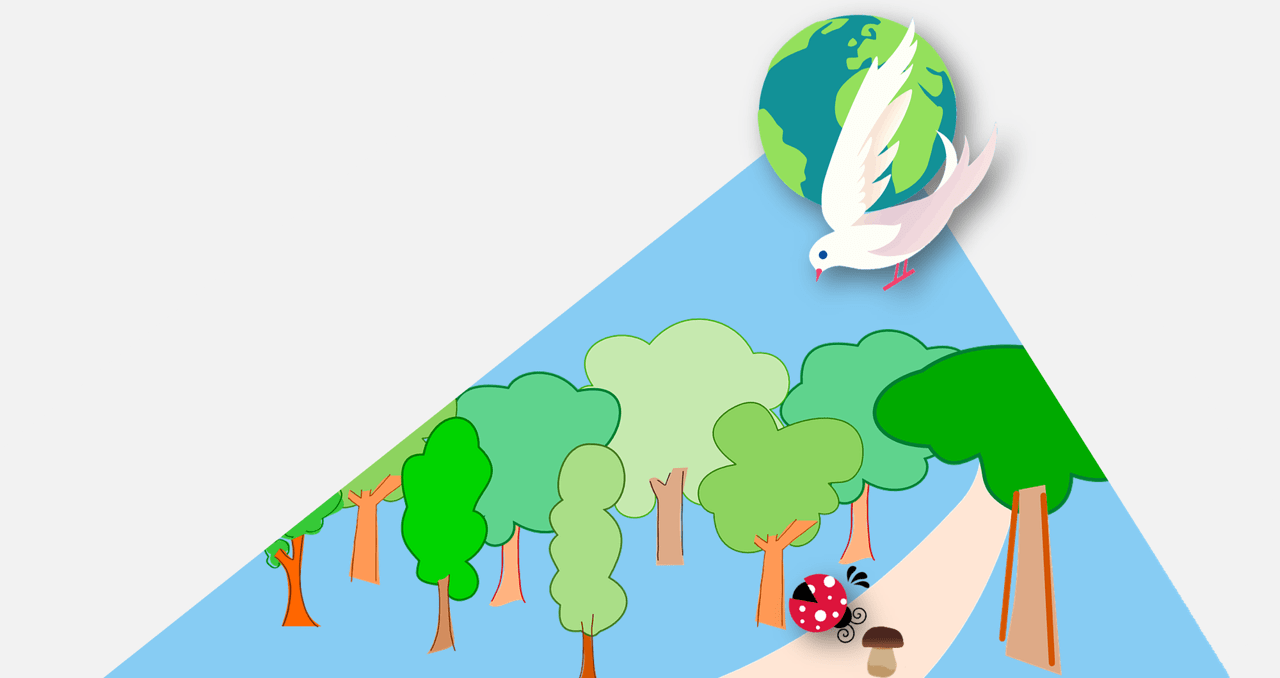
収入がなくなって生活保護を受けること、自分の子どもを学校に通わせること、病気になって健康保険で病院を受診すること、道路を通行すること、みんな人としての「権利(人権)」です。
生活保護を受給することが他の権利と違う特別な恩恵であるという社会の一部の人が確かに持っている偏見を克服しなければなりません。それだけではなく、一部の住民の誤解から生活保護を受けている人たちを守ることも自治体職員としての大切な役割です。
「あの人は生活保護を受けている。恥ずかしいこと」ではありません。そして、「あの人は生活保護を受けているから、税金で食べさせてもらっている」のは(その表現はよくないですが、あえてそう表現するのならば)、生活保護を受給している人だけではなく、私たちみんなです。
(続く)
※本稿をはじめこの連載の内容は筆者の森さんの私見です。
■森 幸二さんの著書紹介(出版年月の新しい順)
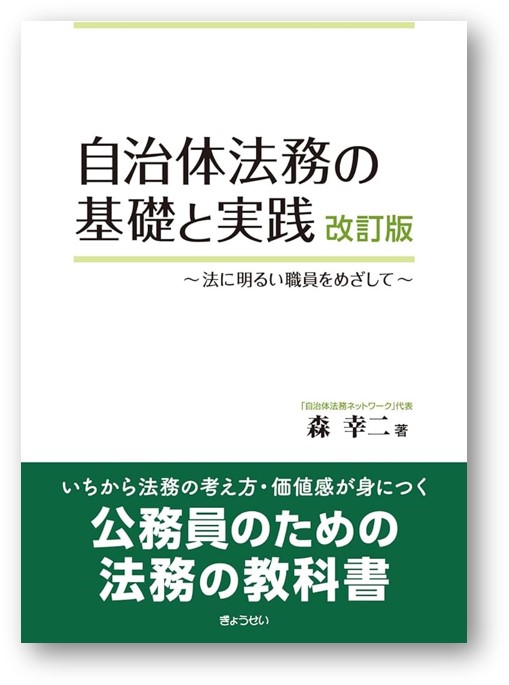
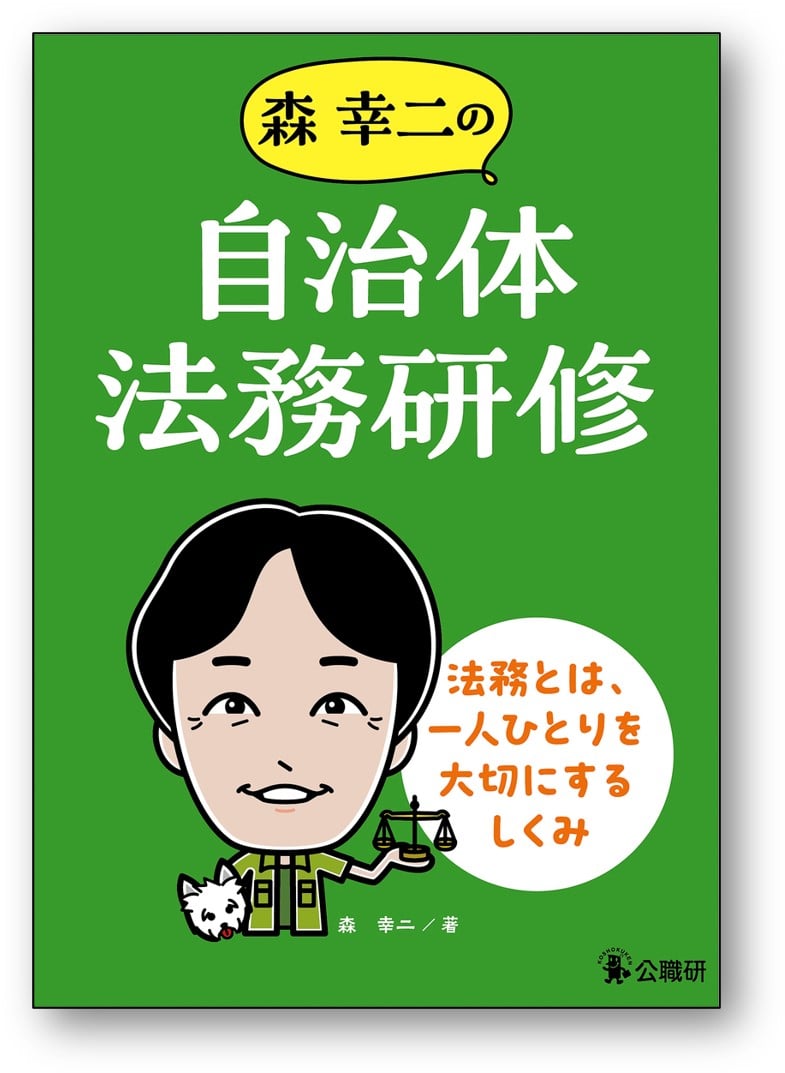

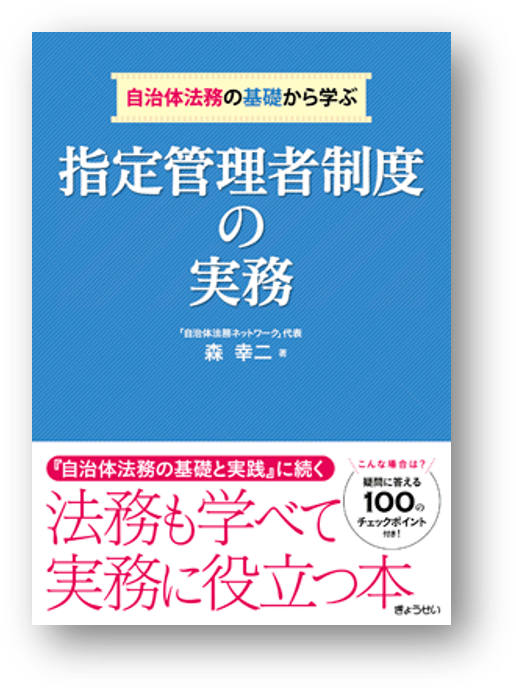
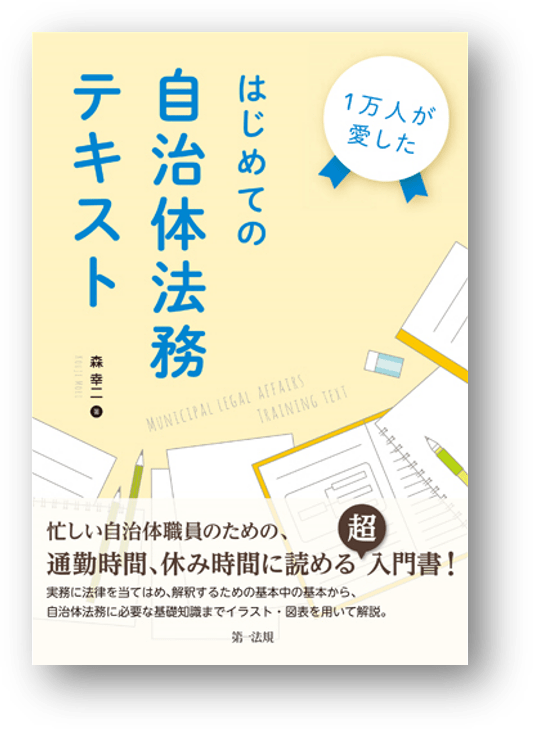
本サイトの掲載情報については、企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。