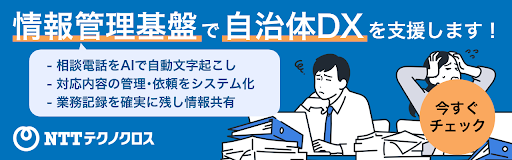増加の一途をたどる小・中学生の不登校児童の数は2023年度の時点で約35万人にも達し(文部科学省調べ)、その受け皿が不足していることが社会課題となっています。こうした中、DNPはGIGA端末に対応しながら3Dメタバースならではの臨場感あふれる空間を構築し、没入感の高い体験ができる「3Dメタバース空間を活用したラーニングシステム」を開発。レノボ・ジャパン合同会社との共同事業として複数の共創パートナーとともに現在まで都内28の自治体・2事業に採用されているほか、2024年8月には新たに静岡県の「令和6年度バーチャルスクール構築等事業委託」に提供しています。
今回は、本事業を推進する大日本印刷(以下、DNP)コンテンツ・XRコミュニケーション本部の正田と、パートナー企業の1社であるPCテクノロジー社(以下、PCテクノロジー)の松野氏に、連携の背景や成果、3Dメタバースを活用した教育の可能性について伺いました。
本記事では、インタビューの後編をお届けします。

▲写真右:PCテクノロジー株式会社 ソリューション事業本部 松野氏 / 写真左:DNP コンテンツ・XRコミュニケーション本部 正田
支援員が子どもたちに接する際、どのような点に注意してサポートしているのですか?
松野(PCテクノロジー):不登校のお子さんたちに共通しているのが、「学校に行けなかった」というつまずきを体験していること。これを払拭するため、「メタバース空間に登校できた」「会話ができた」などの成功体験をステップ・バイ・ステップで積み重ねてもらうことが大切で、そのサポートしていくのが支援員の役割です。

具体的なメソッドの一部をご紹介すると、例えば子どもが3Dメタバース空間に入室したら、常駐している支援員はまず声かけをします。「おはよう。また来てくれてありがとう」「この場所ではこんなことができるよ」といった言葉をかけて、安心できる場所であることを伝えるのです。
ただし、コミュニケーションが苦手な子どももいるので、支援員がしつこく話しかけることはありません。入室後にアバターが壁を向いたまま動かない子もいますが、そうした場合はしばらく見守り、本人のアバターが動き出したりエモートをしたりしたら、さりげなく「一緒にこのゲームやってみる?」と声をかけます。
正田(DNP):そうした運用フェイズでの経験から生まれてきた合言葉が「大人の友だち」ですよね。
松野(PCテクノロジー):そうです、子どもたちにとっての「大人の友だち」でありたいという思いです。先生でも保護者でもない斜め右上の存在として接することで、子どもたちと自然な関係を築いていく。そうすることで、子供からのSOSにいち早く気付くことができます。
正田(DNP):ローンチ時、DNPなりに様々な検証や議論を重ねて3Dメタバース空間を構築しましたが、最後に残された不確定要素が「子どもたちや支援員さんたちは、実際にどのようにふるまい、どこまで機能を活用してもらえるのか」という部分でした。
その点、いま松野さんの発言にあった声がけの習慣や「大人の友だち」というコンセプトなど、いつも前向きな提案をしていただけるPCテクノロジーさんの存在は非常に大きいと感じています。

松野(PCテクノロジー):逆に私たちからみると、DNPさんの課題発生時の対応の速さ、現場に寄り添う姿勢に感謝しています。
支援業務では、開発側とサービス導入側との距離が遠いせいでサービスが機能不全に陥るケースがあるのですが、DNPさんは垣根をつくらず、積極的に現場視察にも来てくれます。
こうした対応が「3Dメタバース空間を活用したラーニングシステム」の提供価値を高めていますし、支援員一人ひとりのモチベーション向上にもつながっていると感じます。
「3Dメタバース空間を活用したラーニングシステム」を運用する中で見えてきた課題や今後の展望を教えてください。
正田(DNP):課題の1つが3Dメタバース空間のさらなる活性化です。ここでの交流を通してコミュニティを広げていく子どもがいる一方で、「メタバース空間に参加すること自体ができない」「参加しても続かない」といったケースも一定数ありますので、動機付けとして様々な追加機能を検討しましたが、GIGA端末のスペックでは実現が難しいケースも少なくありません。
そこで、PCテクノロジーさんからもアイデアをいただいて2024年4月から始めたのが「オンライン部活」です。子どもたちが自分の好きな活動を通して居場所づくりができるよう、これから力を入れていこうと考えています。
松野(PCテクノロジー):部活の例としては、テーマごとに絵を描いて展示スペースに飾る「お絵描き部」、好きなものや昨日良かったものなどを共有する「ポジティ部」、指定されたアイテムを家の中から探してくる「借り物競走部」などさまざまです。
部活をきっかけに子どもたちの交流が深まりますし「歌を歌ってみる」「ビデオチャットで発表する」など新しいアクティビティに挑戦をする機会も生まれています。将来的には子どもたち自身に部活の企画をつくってもらえたらと考えています。
さらなる活性化という点では、先日こんなエピソードがありました。「3Dメタバース空間を活用したラーニングシステム」に通うある子どもに将来の夢を訊いたら、「いつかここの支援員さんになりたい」と答えた子がいたそうです。これはうれしかったですね。正田さんと一緒に大喜びしてしまいました。
そこで浮かんだのが、卒業後も何らかの形で子どもたちが関われる仕組みができないかというアイデアです。教育支援センターでもそうした例はあるそうですが、卒業生が先輩として後輩の相談に乗るような、子どもたち同士の絆が深まっていく場所にしていきたいですね。
一方、SNS等で保護者が子どもの不登校に関する悩みを発信しているコメントは多く、学校や身近な友だちには相談しづらいと感じている方々の存在も気になっています。本サービスの提供価値を高め、社会に根ざしたものにするためには、そうした方々へのケアも欠かせません。
そこで本サービスでは、保護者に向けた情報交換会や進路セミナーなどをオンラインで開催しています。このような子ども〜保護者〜教育機関を包括するコミュニティとしての役割はより強化していきたいと思います。

松野(PCテクノロジー):あとは本サービスの価値を「どう広げていくか」も課題ですね。
正田(DNP):そうですね。現在、私たちDNPの「3Dメタバース空間を活用したラーニングシステム」は、都内28の自治体・2事業に提供しており、2024年8月には静岡県の「令和6年度バーチャルスクール構築等事業委託」にも提供しているほか 、自治体の側でもオンラインの支援空間を出席認定の対象とする検討が始まりつつあります。また、「JAPAN Metaverse Awards 2024」でメタバースジャパン特別賞を、「第12回プラチナ大賞」においてプラチナチャレンジ賞をそれぞれ受賞するなど対外的な評価をいただくケースも増えています。ですが、私たちが考える本サービスの提供価値に比べ、その認知はまだ足りていないと感じています。
例えば、現在の3Dメタバース空間は自治体ごとに独立していますが、今後はそれらを統合し、相互にやりとりできるコミュニティの構築を検討しています。プライバシーを守りながらアカウント認証できる技術と併せてこれを実現できれば、地域や教育機関にとらわれない多様な出会いが生まれるうえ、運用コストの低減にもつながるはずです。その先には、不登校児童の支援に留まらず、社会人向けのリスキリングや交流の場としての活用も見えてくるでしょう。
最後に改めてですが、 「3Dメタバース×教育」という組み合わせは非常に親和性が高いと感じています。その提供価値を高め、真の意味で社会に根ざしたものにするため、今後もPCテクノロジーさんをはじめ様々なパートナーのアドバイスも受けながら、学びやコミュニケーションの可能性を広げる新たな取り組みに挑戦していくつもりです。

※本記事は、DNP Innovation Portに掲載の記事を基にしています。原文記事はこちら(https://www.dnp-innovationport.com/news-report/co_creation_20250226_2/)
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

| 設立 | 1876年10月9日 |
|---|---|
| 資本金 | 1144億6400万円 |
| 代表者名 | 北島 義斉 |
| 本社所在地 | (本社) |
| 事業内容 | ・スマートコミュニケーション部門 |
| URL | https://www.dnp.co.jp/ |
本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。